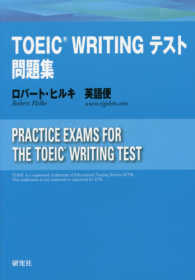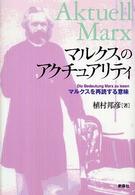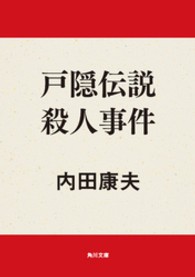出版社内容情報
八年の歳月をかけて創り上げた〈このあたり〉をめぐる物語。日本文学の最前線を牽引する作家が〈このあたり〉にあなたを連れていく。
内容説明
そこには、大統領もいて、小学校も地下シェルターもNHKもある。町の誰も行くことのない「スナック愛」、六人家族ばかりが住む団地の呪い、どうしても銅像になりたかった小学生。川上弘美が丹精込めて創りあげた、不穏で、温かな場所。どこにでもあるようで、どこにもない“このあたり”へようこそ。
著者等紹介
川上弘美[カワカミヒロミ]
1958(昭和33)年、東京都生まれ。お茶の水女子大学理学部卒業。94年、「神様」で第1回パスカル短篇文学新人賞を受賞。96年、「蛇を踏む」で第115回芥川賞を受賞。01年、『センセイの鞄』で谷崎潤一郎賞、07年、『真鶴』で芸術選奨文部科学大臣賞、14年、『水声』で読売文学賞、16年、『大きな鳥にさらわれないよう』で泉鏡花文学賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
こーた
251
長い小説ほどエラい、とおもってしまう傾向がある。でもこの掌篇は特別だ。ことばを適切に選び、極限まで削ぎ落とした世界は美しく詩的ですらある。時間と空間を凝縮し、文字の中に閉じ籠める。神話のようにあいまいで、昔話のように唐突で、落語のように滑稽で、SFのように壮大で、でもどこか懐かしくて、近い。すぐそばにありそうだけど、何だかちょっとズレている。描かれる〈このあたり〉は、ひょっとすると〈あの世〉なのかもしれない。異界は私たちのすぐそばに広がっている。たとえば、本を開けば手の届くほど近く、つまり、このあたりに。2021/01/16
ちなぽむ and ぽむの助 @ 休止中
181
昨日地球が爆発してひと晩自転したらまたいつもの町に戻っていた。おかあさんのちぎれた脚はぶじくっついて、私の飛び散った脳漿はきちんと脳におさめられた。私は昨日までの世界がもうどこにもいないことがかなしくて少しだけ泣いて、いまここにある地球はクーデターの準備に忙しいから私もいそいそと銃やら甲冑(おじいちゃんが家宝だから大切に、と言っていたやつ)やら揃えおく。なんだか遠足みたいでわくわくしてきて、お外で食べるお弁当を思うと今日はいい日だと思う。たとえ明日この町がなくとも、私たちの日常はどこまでも平穏だ。2019/12/05
ケンイチミズバ
137
一話が3~4ページもない短編で古川日出男氏のあとがきがいちばん長い。現実にありそうな光景も奇譚のような話も結びで笑いや戸惑いになる。子供の頃に見た聞いたあったことを基に想像力で膨らませた世界のようにも感じられ、懐かしさもある。どの話にも重なる登場人物がおり、話しが短か過ぎて先に登場した人を何度も戻って読み返すこともできます。「埋め部」の話はアルバイトが年賀状を配達するのが面倒になり、公園や海岸に埋めたというニュースが昔はよくあったなと、今は年賀状を書く人も減ってそういうことも無くなったのかな。なんて。2020/01/22
ふう
101
かなりおかしな人たちの住む町だけど、ぎすぎすしてなくて、まあそんなものかと受け入れれば案外住みやすい町かもしれません。町の人が行きたがらないスナック愛で、ママさんが歌う歌は昭和そのもの。わたしもよく歌いました。そのせいでしょうか。「このあたり」は何だかあの頃の「あのあたり」のようにも思えて、懐かしさを憶えました。2020/01/21
エドワード
99
私が訪れた風変わりな町。農家の義眼おじさん、スナック愛のおばさん、犬学校の校長先生らが住んでいる。六人家族の多い公団住宅がある。意地悪なかなえちゃんは不良になるが、フランスへ留学してデザイナーになり「郷土の誇り」になる。かなえちゃんのお姉さんは恐山の大イタコになり、遠足で拾った白い鳩のような、人間の姿に変わるものと暮らす。鳩が巨大隕石を破壊して地球を救い、お姉さんの銅像が立つ。へえっ!支離滅裂だけど面白い!扉絵が不気味だけどどこか可愛い!令和元年最後の本が川上さんで本当に良かった。それでは良いお年を。2019/12/30
-
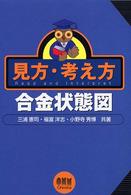
- 和書
- 見方・考え方合金状態図