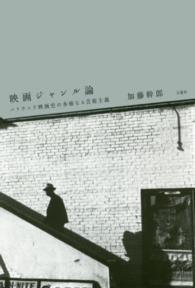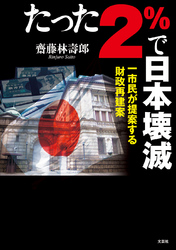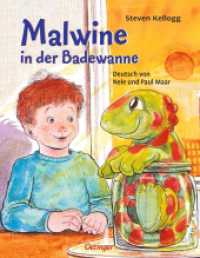出版社内容情報
小林家の〝サーガ〟、完結編
あの戦争を境に様変わりしていく東京・山の手と明治生まれの祖父の姿。作家・小林信彦の青春時代を緻密に描く自伝的大河小説。
内容説明
1946年12月、東京・青山。疎開先から戻った「私」の一家は、母方の祖父の家に身を寄せる。明治生まれの祖父の時代精神とその哀しみ、そして様変わりしていく山の手を見つめながら、「私」は青年へと成長していく―。人生と時代への諦観と進取の志に揺れる青春を緻密に描いた作家・小林信彦の自伝的傑作。
著者等紹介
小林信彦[コバヤシノブヒコ]
昭和7(1932)年、東京生れ。早稲田大学文学部英文科卒業。翻訳雑誌編集長から作家になる。昭和48(1973)年、「日本の喜劇人」で芸術選奨新人賞受賞。平成18(2006)年、「うらなり」で第54回菊池寛賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
-





ミスランディア本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Willie the Wildcat
55
終戦直前から戦後にかけての山手の変遷と、自身の成長を通した時勢の移り変わり。家の浮き沈みを淡々と語る一方で、朝鮮戦争勃発に伴い原爆を恐れ、公職追放解除で知る級友の素性に気が晴れる著者の心情。大戦が齎す心身そして、思考への影響が印象的。文字との繋がりも興味深い。古本屋、図書委員はまだしも、”理のある”万引き?!祖父の死が精神的な終戦処理の始まりであり、滝本との再会が終戦との決着という感。2017/09/12
浅香山三郎
18
小林信彦さんの自伝的作品。母方の祖父との関係に焦点が当てられたもので、これまで、随筆の方では部分的に書いておられたが、ここまで掘り下げられたのは初めてではないか。戦中・戦後の一家の流転、それを記録する工場経営者としての姿、横浜の米軍相手の商売人の実態など、主人公の眼からみた世の中のありやうの観察は鋭くて、またユニークでもある。いくつかの小林さんの作品世界とも互いに繋がり合ふので、その点でも面白かつた。2019/01/29
niisun
17
戦中から戦後にかけての市井の人々の生活を描いた作品に興味があるので手に取ってみた作品ですが、もう少し小林氏の作品を読んでから読まないといけない作品だったかもしれませんね。結構「これについては『○○』という作品に詳しく書いた」みたいなところが多くて、全体像が掴めませんでした…。 それでも、戦中戦後の東京市区や横浜の姿が詳細に描かれていて、とても面白かったですねぇ。特に、隅田川沿いや青山周辺、横浜の元町や中華街あたりの描写が細かく書き込まれていて、当時の風景が浮き上がってきます♪2015/10/12
阿部義彦
10
小林信彦の文庫、出たばかりです、小説の形はとっているが、かなり自叙伝に近いです。昭和の生き証人としての山の手の変遷と少年から青年期にかけての、性に対する衝動そして本を万引きした事等が赤裸々に語られます。今回の主役は母方の祖父で沖電気の創設に関わった人物。これ以外にも三部作の片割れとして、「 東京少年」と「ド日本橋バビロン」が有るとの事なのでそちらもいずれ読みたいです。私が小林信彦さんを知ったのは仲の良かった大滝詠一さんを通してです。小林さんには長生きして再び新作を読ませて頂きたいです。2015/09/05
MADAKI
1
【自伝風エッセイ】文筆家の筆者が子供時代から青年時代を振り返りつつ自身のルーツへ踏み入っていく作品。東京に住みようになってから、昭和の東京の空気を味わえる作品が好きになったが、これもそうした古き(必ずしも良くはないが…)東京の匂いを感じられる。2016/12/03
-
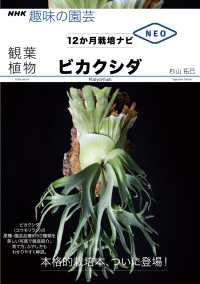
- 電子書籍
- 観葉植物 ビカクシダ NHK趣味の園芸…