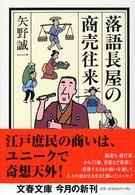出版社内容情報
日本人が初めて持った歴史観、庶民の風土、史料の語りくち、「手ざわり」感覚。圧倒的国民作家が明かす、発想の原点を拡大文字で!
内容説明
日本人の底の底には無思想という思想、簡単に言ってしまうと美意識があるのではないかと思う―日本人が初めて持った歴史観、庶民の風土、「手ざわり」感覚で受け止める伝統的美人、義経という人気者、幕末三百藩の自然人格。歴史小説に新しい地平を開いた圧倒的国民作家が、自らの発想の原点を解き明かした好エッセイ集。
目次
私の歴史小説(庶民の風土;生活史への興味 ほか)
歴史のなかの日常(トシさんが歩いている;歴史を見る目 ほか)
歴史のなかの人間(見える目と見える場;義経という人気者 ほか)
日本史と日本人(日本的正義感;藩というイメージ ほか)
わが小説のはじまり
著者等紹介
司馬遼太郎[シバリョウタロウ]
大正12(1923)年、大阪市に生れる。大阪外国語学校蒙古語科卒業。昭和35年、「梟の城」で第42回直木賞受賞。41年、「竜馬がゆく」「国盗り物語」で菊池寛賞受賞。47年、「世に棲む日日」を中心にした作家活動で吉川英治文学賞受賞。51年、日本芸術院恩賜賞受賞。56年、日本芸術院会員。57年、「ひとびとの跫音」で読売文学賞受賞。58年、「歴史小説の革新」についての功績で朝日賞受賞。59年、「街道をゆく“南蛮のみちI”」で日本文学大賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
i-miya
53
2013.07.24(初読)司馬遼太郎著。 (カバー) 日本人の底の底には蒸しそう、無思想という美意識がある、 義経という人気者。 幕末300藩の自然人格。 (解説=江藤文夫) 歴史を見る目は遠近感を退ける。 乃木希典伝のうち、最も優れた一つ、宿利重一、『人間乃木将軍』。 『おお、大砲』。 和州高取の小藩に伝わる古風な大砲。坂道を転げてくる砲丸、に逃げ惑うという天誅組の一人。 三日間ほど耳鳴りがした。 毎日新聞社コア・ブック。 岡本博氏。 2013/07/24
たつや
45
江藤文夫さんのインタビューを書籍にまとめられた本。冒頭の「先生と私」は司馬さんへの愛が感じられました。また、司馬さんが自分のおじいさんについて語り、まだ調べてないけど、調べてたら、書いてたのか?興味深い。親戚に赤穂の志士がいたらしいと、特殊な自身の家紋があったと、おっしゃってますが、そういえば、「忠臣蔵」を書いてないんですね。毎年暮れに読みたくなるような忠臣蔵を書いておいてほしかった。2016/11/09
i-miya
43
2013.08.09(つづき)司馬遼太郎著。 2013.08.08 史観と史眼。 奇談、奇説が真実に的を得ていることがある、が、しかし、百に一つ本当のことがあるにしても・・・。 残り99に対する自分の目が曇ってしまう。 史料はファクトに過ぎない。 ファクトを出来るだけ多く集めないと真実が出てこない。 思考がファクトのところで止まっていては、ファクトの向こうへいけない。 ファクトは親切に見なければいけない。 2013/08/09
i-miya
39
2013.08.18(つづき)司馬遼太郎著。 2013.08.17 日本へ亡命を勧める伊東祐亨。 薩摩藩士、海軍は神戸海軍操練所(勝海舟の半官半民塾)で学ぶ、塾頭は、坂本竜馬、その後戊辰戦争は一兵士として戦う。 手紙の中の、言葉遣い、語尾の微妙さ、大事。 ◎『歴史のプラスとマイナス-予期せぬ歴史の転換-人間を呑み込む』の章。 『夏草の賦』に取り上げられた一領具足の制度、江戸時代300年間で死滅の間、幕末に開花する。 2013/08/18
i-miya
38
2013.08.15(つづき)司馬遼太郎著。 2013.08.15 ◎史料の語りくちの章。 ◎明治維新くぐり抜けてきた軍人。 日清戦争。 日本の連合艦隊司令官、伊東祐亨(ゆうこう)。 清国北洋艦隊司令官、丁汝昌。 北洋艦隊は連戦連敗。 威海衛の奥に潜んで出てこない。 この丁、よくまあ清国で存在しえた、奇跡である。 ちゃんとした人である。 伊東祐亨は丁のことをよく知っていた。 M20年代、丁は、北洋艦隊を率いて日本を訪問している。 日本に対するデモンストレーションであった。 2013/08/15