出版社内容情報
明治三年に生まれ、保線作業の近代化とともに消えた国鉄の「道床搗き固め音頭」。九十年間それを唄い継ぎ、鉄路を守り続けてきた男たちの物語。第15回大宅賞受賞作
内容説明
新橋―横浜間に鉄道が敷かれた明治初年以来、線路工手が唄い継いできた作業唄「道床搗き固め音頭」は、工具の革新によって昭和30年代に消滅した。各地でかつて唄われた音頭を発掘しつつ、底辺で鉄路の安全を守り続けた男たちの苦闘の歩みと急ぎすぎた日本の近代化の歪みを鮮やかに捉えた力作。大宅壮一ノンフィクション賞受賞作品。
目次
はじめに 線路と作業唄
1 北の線路
2 名人の眼
3 村の線路班
4 建主改従
5 消えた線路
6 金看板
7 音頭の流れ―伝説のジョーンズ工手長
8 音頭のリズム
9 保線の魂
10 陽炎の彼方へ
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ひねもすのたり
6
第15回(84年)大宅壮一ノンフィクション賞を受賞した本書はかつて人力に頼っていた鉄道保線の歴史とそこに関わった人々を描いたノンフィクションです。 タイトルの[唄]とは彼らが線路の搗き固め作業の際タイミングを合わせるために唄われた作業歌のことです。[唄]を足掛かりに日本全国の保線マンにインタビューが行われていますが、その地形から屈指の難所と言われた北陸本線/親不知の線路を守った人々の仕事ぶりが心に残りました。 ↓続きます。 2014/01/28
Hiroki Nishizumi
2
線路というものの保守が地盤によって大きく左右されること、そして日本の線路が不十分な状態であること、また保線の仕事は恵まれていないことなどが良く分かった。昨今相次ぐJR廃線は単純な収益以外にこのような要因があった訳だ。そして作業唄の多くが実際には作業進行時にはあまり歌われていないことも勉強になった。2020/07/27
moonanddai
2
(おそらく)明治初期に政府に雇い入れられた外国人技師が伝えたと思われる、線路保守作業の「かけ声」が発祥とのこと…。確かに「かけ声」が発祥とすれば、労働歌やブルースではなく、歌詞等が洗練された訳でもなく、作業の機械化とともに消えてしまうのも運命かも…。それだけではなく保守作業という純粋に技術的な分野に、(時代の流れの中ではあるが)精神主義を持ち込んだことによっても同じなのかもしれない。ではあるが、それでも線路保守に情熱を傾けてきた人たちがいたことも事実である。JR北海道も原点に帰るべきでは…。2013/12/29
-
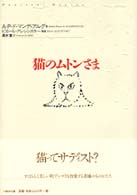
- 和書
- 猫のムトンさま








