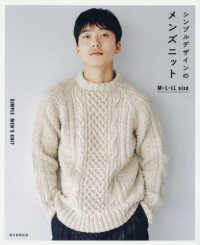出版社内容情報
塚原卜伝、宮本武蔵、一刀斎、柳生但馬守など有名剣豪の実像は?超人的な剣聖流祖を俎上にのせ、その剣技の実態を余す所なく描く
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
出世八五郎
18
名のある剣豪とその流派を紹介したもの。始まりは戦国初期になるが資料乏しく実質的に紹介されるのは、資料のある塚原卜伝や上泉伊勢守の時代から幕末まで。あまりにも多くの剣豪が幅広く紹介されるので憶えるのが苦しいが、有名所を抑えとくだけでも面白い。剣豪小説を読む前に本書が役に立つと思う。個人的には最近、南条範夫に興味を持っていた処、積読に著者の作品があり読んだ次第で、以前、売却しようとしていた作品。数多い剣豪に興味があればお勧めで剣豪ガイドブックといってよく、エピソード豊富で面白い。2015/08/28
SKH
9
剣豪考察。いつの世も「武勇伝」は、話を盛りがちで胡散臭く、ちょっと痛い。勇ましさが増すほどマヌケ感も増すという、負のスパイラル。剣豪、流派の名も尊大さが際立つと、キラキラネームを見てるよう。笑える。剣士に対する淡い幻想は砕け散り、清々する。199X。2014/09/01
Hiroki Nishizumi
5
興味深く読めた。部外者の目で先達の評価をしているところが面白く感じた。また、すらすらとした足運びなどの奥義は取り上げているだけで解説出来ないところも正直で良いと思う。2014/02/24
saladin
2
古い本だが、さすが剣豪ものを数多く物した著者だけあって興味深く読める。どうやら戦国初期の塚原卜伝など実戦の場数を踏んだ剣士を高く評価しているよう。なるほど実際に強かったのは彼らだろう。江戸時代、太平の世になるとそもそも命懸けで戦う必要などなくなる。剣士もスケールが小さくなり、小手先の技術ばかりが発達した”道場剣法”になっていったのだろう。ただ、幕末期には時代の趨勢によって再び剣法が興隆するが、時すでに剣の時代ではなく…。新選組の面々を”問題にならぬ三流だ”と歯牙にもかけないので、新選組好きは憤慨するかも。2020/03/22
両
2
系統の正伝のみにこだわらず、人物としては下とか、実力はたいしたことが無かったのではないかなどと歯に衣着せず欠いてあるのが面白い。もっとも、門下だと困るかもしれないが、そのあたりも含めて。2013/05/14