出版社内容情報
大正七年から完成まで十六年の歳月を費した世紀の難工事・丹那トンネル。その土と水と人との熱くすさまじい闘いを描いた力作長篇
内容説明
丹那トンネルは大正7(1918)年に着工されたが、完成までになんと16年もの歳月を要した。けわしい断層地帯を横切るために、土塊の崩落、凄まじい湧水などこに阻まれ多くの人命を失い、環境を著しく損うという当初の予定をはるかに上まわる難工事となった。人間と土や水との熱く長い闘いを描いた力作長篇小説。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ミカママ
444
記録文学の巨匠・吉村さんの、再び「トンネルもの」。『高熱隧道』が残された設計図と回想録から組み立てられた小説であるのに比べて、こちらは存命者からも話を聞け、登場人物は大部分実名だそうだ。だからこそよりリアルであり、かえって読みにくいという読者も多いだろう。事故で直接犠牲になった方々はもとより、丹那盆地から水が消えていく描写もキツかった。普段何気なく利用しているトンネル(WiFiが飛んでねぇよ!などと腐ることなく)、功労者たちに想いを馳せたい。2019/05/12
しおつう
21
昔のトンネル堀りは危険がいっぱい。しかも7㎞超えの長距離ともなると危険も時間も労働者も倍増。今回も様々な難関があった。予想される事故以外にも大きな障害が現れ、まさにそれがこの小説の隠し味かもしれない。自分が何気に通っていたJRの大津↔️山科のトンネルが日本で2番目に掘られたもので、多くの事故犠牲者が出ていたことにも今更ながら驚き。それにしてもこの小説にして『闇を裂く道』…。もう少し気のきいた題名にしてほしかった。2017/11/14
bluemint
20
伊豆の丹那盆地の下を掘り進む人間たちを描く。圧倒的な自然の力に押しつぶされながらも、当時の考えうるすべての力を結集し何とかねじ伏せる。しかし、ページが進まないのだ。物語ではなく、厳密さにこだわる報告書なのだ。作業員とか工事主任など架空の人物を主人公に設定し、彼を狂言回しにすればより読みやすくなったのではないか。トンネルの先が地震による断層のズレで山の中に消えてしまった、トンネルの上の丹那盆地では水が枯れ農業が全滅した、などの挿話はゾッとする。 2018/07/29
Cinejazz
16
鉄道院初代総裁・後藤新平の創案による、東海道線の熱海と三島を結ぶ丹那トンネルは大正7年に着工、7年間で完成の予定であったが、足かけ16年の歳月を要し昭和9年に完成した。断層地帯を横切る難工事の期間中に、関東大震災(T.12)、北伊豆地震(S.5)が丹那断層を直撃し、烈しい湧水、土塊崩落などで67名もの人命が失われた。坑道掘削による丹那盆地の渇水被害問題では、田畑の用水、飲料水を返せと叫ぶ住民の殺気だった様子が記録されている。自然の測り知れぬ脅威と人間の燃える不屈の闘いを描いた、吉村昭氏 渾身の長編小説。2021/11/13
shizuka
16
灼熱地獄『高熱隧道』の次は水攻め地獄。事故のないように進めてはいるが、ゼロには押さえられない。閉じ込められてしまった坑夫たちを必死の思いで救出する側、暗闇で助けをひたすら待つ側。幸い助かったので両側から事故の内容が克明に記されていて、手に汗握りながら読んだ。中盤からは水に悩まされ、それがトンネル近くの村の井戸を枯れさせる原因に。村民の怒りが痛々しく辛かった。トンネルのため協力したのに、水で困ってると訴えてもないがしろにされ。大正時代のこのトンネル工事から、東海道新幹線開通までの鉄道の歴史に静かに感動した。2014/01/16
-
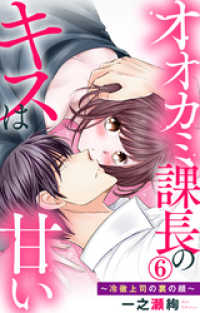
- 電子書籍
- オオカミ課長のキスは甘い~冷徹上司の裏…








