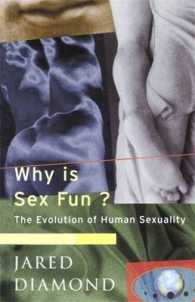内容説明
三十を過ぎても定職につかず、漫然と生きる長井代助には、かつて愛した女性を親友に譲った過去があった。彼女と再会した代助を襲う衝動、それは真実の愛か、理に悖る愛か―。近代人とエゴイズムの問題に切り込んだ『それから』。罪を負った代助の“後日の姿”を冷徹に見つめた『門』。永遠の名作二篇を収める。
著者等紹介
夏目漱石[ナツメソウセキ]
慶応3(1867)年、東京に生れる。帝国大学文科大学英文科卒業。東京高等師範学校、松山中学、第五高等学校の教職を経て、イギリスに留学する。帰国後、第一高等学校、東京帝国大学で教鞭をとるかたわら、『吾輩は猫である』『坊っちゃん』を執筆。明治40(1907)年より朝日新聞社員となる。以後、同新聞に『虞美人草』『三四郎』『それから』『門』を発表、明治43(1910)年、胃潰瘍のため吐血してからは病いと闘いながら『彼岸過迄』『行人』『こころ』『道草』を書いたが、『明暗』を執筆中の大正5(1916)年死去した(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。