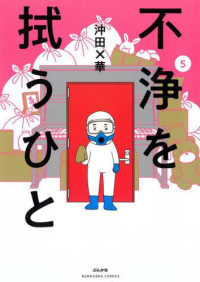内容説明
法律は文化や歴史を反映する鏡。権力の道具にもなれば、暴政を防ぐ楯にもなる。「奇妙な」法にもその国・地域の事情がある。古今東西の法律を読み解くと、新たな世界像が浮かんでくる。
目次
第1章 古代文明と法(法典のはじまりのころ;古代エジプト時代は神が裁く ほか)
第2章 近代法以前(ヴァイキングと議会;イギリス不文憲法のルーツ1…ジョン王とマグナ・カルタ ほか)
第3章 イスラーム世界の罪と罰の考え方(脅威のイスラーム;イスラームの起源 ほか)
第4章 現代社会と各国の法律(弁護士多ければ訴訟多し…いきすぎたPL法;弁護士多ければ産科医が減る? ほか)
第5章 いろいろある世界の法、規則、警告(タイ;シンガポール ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mitei
199
21世紀もだいぶ経ってしまったので読んでみた。法律って各国色々あるもんだなと知った。ハンムラビ法典がおそらく現存する原点だな。2020/03/24
ヒダン
14
前半は法律の世界史のような内容でかなりしっかり書かれていて、途中からは世界の珍しい法律集のような読みやすい読み物になっていく。西洋では国王が不透明に管理していた権力を市民にも分かるよう開放したという法=権利の感覚がある。東洋、特に中華圏では統治者が罰則を設けることが法であり法で縛られていると思ってる。イスラム圏ではクルアーンの記述、及びムハンマドの言葉は基本的に絶対である。このように文化が違えば法律も、法律に対する考え方も違う。イスラムについて書かれた3章は初めて知ることも多く分かりやすくて有意義だった。2016/06/17
mazda
8
かなり難しい内容でした…。読み切れず、今後再読したいと思います。2020/06/09
駒子
7
初の文藝春秋「世界地図」シリーズ。古今東西の法律を取り上げる。第三章「イスラーム世界の罪と罰の考え方」が特に面白かった、2014/08/10
うえ
5
簡単な本かと思ったが詳細。ただ予めローマ法やアテナイ法,イスラム法や東洋法を知らないと難かも。穂積陳重だけでなく英米法でもグラッドストンやコークをきちんと紹介しており好感がもてる。イスラムでも五十嵐一やラシュディを扱っており専門家のタブーから免れている。それにしてもイスラム自身は寛容であることを謳うが,寛容な国々がイスラムに寛容なことをイスラムはどう考えるのか?現時点では,偉大なイスラム法を民主主義者がやっと理解しはじめた!と考えてるとしか思えない。その視点で書かれた邦書は殆どない。2014/07/07