内容説明
「デモグラフィ」とは、出生・死亡・移動などの人口統計全体、あるいは人口の研究を指す言葉である。つまり本書は、新たに発掘された史料、進展してきた歴史人口学の成果を踏まえ、大正期を人口という窓を通してながめてみよう、という意図のもと書かれた。その視点で検討してみると、従来「デモクラシィ」の時代と呼び習わされてきた大正期も、かなずしも明るく進んだ面ばかりではなかったことが分かる。大正時代を捉え直す意欲的な試みである。
目次
第1章 明治と昭和の狭間で
第2章 大正期の全国人口
第3章 第一次世界大戦と戦時景気
第4章 大正五年の出生力
第5章 死亡率上昇―女工と結核
第6章 スペイン・インフルエンザ
第7章 人口指標のいろいろ
第8章 国勢調査
第9章 大正末年の人口
著者等紹介
速水融[ハヤミアキラ]
1929年生まれ。慶応大学卒。同大学教授、国際日本文化研究センター教授を経て現在、麗沢大学教授。専攻は日本経済史、歴史人口学。2000年、文化功労者に
小嶋美代子[コジマミヨコ]
青山学院大学卒。東洋英和女学院大学大学院社会科学研究科を経て、麗沢大学大学院国際経済研究科博士課程修了。現在、慶応大学国際センター勤務。経済学博士
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
sfこと古谷俊一
1
歴史人口学の人が大正時代の国勢調査やその他の調査を読み解く。15年とは社会が大きく変わるのに十分な長さなんだな。インフルエンザにマスクとうがいは、スペインかぜ当時の啓蒙内容で、ウイルス発見前の知識だったのね。2009/07/26
いちはじめ
1
デモグラフィとは人口統計学のことだそうな。大正時代を人口統計データから読み解こうとする試みは、刺激的で示唆に富む2004/01/20
編集兼発行人
0
大正期を中心にした我国における世間の模様に関する考察。人口の統計を基本的な資料として用いつつ往時のマクロ動態を詳述するという構成。第一次産業から第二次産業への転換や交通教育エネルギー情報など社会的なインフラの拡大を通じて様々な指数が高度経済成長の如き倍増化を辿る傾向であり其れを背景として結核やスペインインフルエンザの流行による死亡率の増加を上回る死産率の低下が都市や農村と両者の間との構図に著しく影響を及ぼし対岸の火事に似た戦時下の地理的な要因により対アジア貿易を殆ど独占できた幸福な時期であったことを理解。2014/10/19
MIRACLE
0
大正時代の15年間の民衆の生活状態について、大正期の人口指標の変化をもとに、総論・人口・景気・出生 死亡・インフルエンザ・その他の指標・国勢調査の順に、のべた本。個人的には、出生率が電灯の普及とともに、下落していることが、興味深かった(75頁)。2013/08/25
-
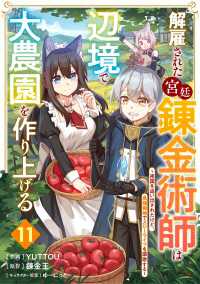
- 電子書籍
- 解雇された宮廷錬金術師は辺境で大農園を…
-
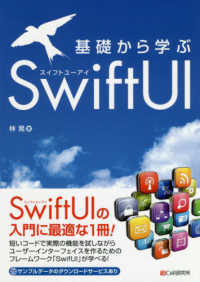
- 和書
- 基礎から学ぶSwitUI






