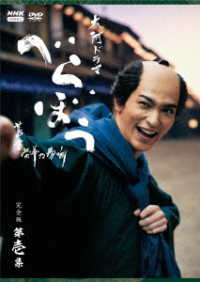出版社内容情報
時は文化5(1822)年。本屋の“私”は月に1回、城下の店から在へ行商に出て、20余りの村の寺や手習所、名主の家を回る。上得意のひとり、小曾根村の名主・惣兵衛は近ごろ孫ほどの年齢の少女を後添えにもらったという。妻に何か見せてやってほしいと言われたので画譜――絵画の教本で、絵画を多数収録している――を披露するが、目を離したすきに2冊の画譜が無くなっていた。間違いなく、彼女が盗み取ったに違いない。当惑する私に、惣兵衛は法外な代金を払って買い取ろうとし、妻への想いを語るが……。
江戸期の富の源泉は農にあり――。江戸期のあらゆる変化は村に根ざしており、変化の担い手は名主を筆頭とした在の人びとである、と考える著者。その変化の担い手たちの生活、人生を、本を行商する本屋を語り部にすることで生き生きと伝える“青山流時代小説”。
内容説明
本を行商して歩く私が見たものは、本を愛し、知識を欲し、人生を謳歌する人びとだった。
著者等紹介
青山文平[アオヤマブンペイ]
1948年、神奈川県生まれ。早稲田大学第一政治経済学部卒。経済関係の出版社勤務、フリーライターを経て、2011年『白樫の樹の下で』で松本清張賞を受賞。15年『鬼はもとより』で大藪春彦賞、16年『つまをめとらば』で直木賞、22年『底惚れ』で中央公論文芸賞と柴田錬三郎賞をダブル受賞する(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
starbro
299
青山 文平は、新作中心に読んでいる作家です。本書は、行商本屋時代幻想譚連作短編集でした。オススメは、『鬼に喰われた女』です。 https://books.bunshun.jp/ud/book/num/97841639166822023/04/17
パトラッシュ
260
生活にゆとりができた江戸後期の地方では、読本や絵草紙だけでなく本物の知識を求める人が増えていく。そんな農村を商圏に学術書である「物の本」を扱う本屋の平助の目を通して、書物を介して接した人間模様を語っていく。男女関係のもつれや最新の医術修得など、様々なことを読書で知れば知るほど却って解決が難しく困り果てる姿は滑稽で哀しい。農村まで国学や歌学が広がる過程で起きた悲喜劇かと微苦笑を誘う人情物だが、こうした知識のしみ込んだ名望家層が幕末維新期に地方の指導者となるのだから、いわば動乱前の人を育てる物語として読める。2023/05/17
KAZOO
201
先日、江戸時代の貸本屋の話の「貸本屋おせん」を読んだばかりですが、これは江戸時代の本を売る話です。短編というか中編が3編収められていて、当時の本屋の状況あるいは出された本などをものすごく克明に調べられています。若干オカルト的な話(鬼に喰われた女)もあったりしますが、わたしにとっては総じて楽しい話ばかりでした。塙保己一の「群書類従」や専門的な医書の話などはよく調査されていると感じました。続きが読みたいです。2024/02/29
みっちゃん
176
良き、善き。重い本を行李に納めて担ぎ、城下から山を超えて。得意先は在所の名主達。彼らは当時の知識人であり、その本を慈しむ思い、集めたい気持ち、そしてその内容について誰かと語り合いたいという願い、わかりすぎる程わかるけど、当時は一部の人にしか許されぬ贅沢だったんだね。本について語るうちに話題にのぼるのは、地道にこつこつと、慎ましく暮らす市井のひと達の生きる喜び、そして苦しみ。大切なひとと共に過ごし、愛し、幸せを願う気持ちはいつの世にも変わることはない。最後の最後にかの本屋の切なる願いが叶うのも好ましい。2023/05/09
のぶ
168
今まで読んだ青山さんの本では一番読みやすかった。江戸時代の文政の頃、城下に店を構え、四日ほどかけて二十ほどの村を行商して回る本屋、松月堂の主人平助が主人公。行商でまわるのは村の名主や寺や手習い所。そこで出会うさまざまな不思議で不可解な出来事たち。平助が「本屋」としてその不思議を解いていく。本屋ならではの視点や解釈。本を扱うものとしての平助の姿勢に思わず背筋が伸びる。いつも青山さんの作品に出てくる主人公は真っ直ぐな人が多いが、本作でもそれがよく出ていた。三作の中では「初めての開板」が特に良かった。2023/03/26
-

- 電子書籍
- 御曹司との恋に秘密はつきもの【タテヨミ…
-
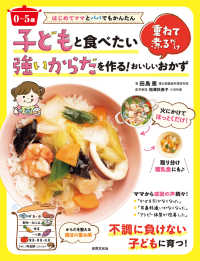
- 電子書籍
- 〈0~5歳〉子どもと食べたい強いからだ…