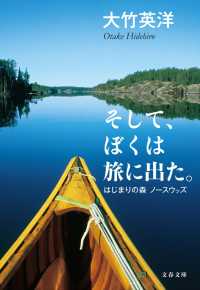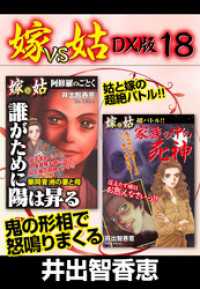出版社内容情報
今年も北星余市高校には問題が続出。薬物、暴力、イジメ・・・。でも寄り添い続けることでしか生徒の心は開かない。奮闘記第二弾!
内容説明
母校北星余市高校から横浜市教育委員へ―。イジメ、薬物、飲酒、援助交際…。場所はかわっても、ヤンキー義家は教育の現場で闘い続ける。
目次
1 ヤンキー母校を去る
2 北の小さな私立高校
3 夢は逃げていかない
4 教師論
5 指導部な毎日
6 ほんとうの信頼関係
7 終わらない闘い
著者等紹介
義家弘介[ヨシイエヒロユキ]
1971年3月31日、長野県長野市生まれ。中学生の頃より「不良」と呼ばれるようになり、1987年、進学した高校から退学処分を受ける。同時に家からも絶縁され、児童相談所を経由し里親の元へ引き取られる。北星学園余市高等学校の全国からの中退者本格受け入れの初年度となる1988年、傷心の思いを引きずりながら同校の門を叩き編入。1990年、明治学院大学法学部法律学科入学。卒業後は大手進学塾に就職。1999年、母校、北星学園余市高等学校に社会科教師として赴任し、2003年春、初めての卒業生を送り出した。2003年4月から生活指導部に所属。2004年度は生活指導部長を務めた。2005年春、同校を退職、横浜市教育委員に就任した
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
再び読書
13
義家先生が何故北星余市高校を去らなければならなかったのかが、冒頭で述べられるが、愛してやまない母校での戦いが語られている。とにかく必死で生徒に立ち向かう義家先生の熱が伝わる。また水谷先生も何度も述べている薬物への危険がここでも語られている。まだ本当に子供たちの周りにある危険が親にも認識されていない事が、ひしひしと感じられる。2014/08/29
1.3manen
5
著者は1971年生れ。微妙に評者より1つ上の学年だな。57ページには生徒の目線を黒板に釘づけにする技術をマスターしたと書いてある。これも時代でそろそろパソコンで説明することが主流になるだろう。iPadで生徒も学習することが小学生でもできつつあるので。集団授業も少子化の時代にどれだけの効果があるのか、検証する必要もあろう。学校の生徒のときに問題児だった人が、教育委員を務めるとは思っていなかっただろう。しかし、人生や社会は適材適所になっているかどうかというと、必ずしもそうでない。学校は所詮きっかけでしかない。2013/02/10
かもやん
1
義家さんが北星余市高校で考えたことが詰まっている一冊。子どもとの接し方や指導のあり方について、今の大人たちに警鐘を鳴らしている。「連携なき分業」により生徒への責任を他になすり付ける大人。「成長」に責任を持たずに「人生」に責任を持とうとする大人。優しさと甘えをすり替えている大人。 常に自分を見つめ直しながら教育に向き合って行かなければならないなと戒められました。 気になるところに付箋を貼っていたらかなりの量になってしまった。それぐらい、心に響く言葉、考えさせられることが多く詰まった本だったと思う。2013/03/19