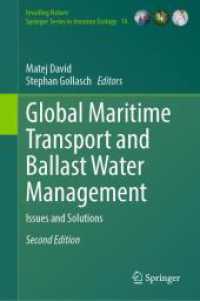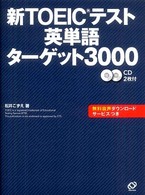出版社内容情報
幕末、初めて体験する為替レートに苦慮する男たち。列強の圧力、謀略……。新田次郎賞受賞の名作が英訳、全面改稿を経て今甦る!
内容説明
マネー戦争の原点ここにあり!幕末初の為替レートはいかに設定されたのか。幕府瓦壊の要因を経済的側面から描き、新田次郎賞を受賞した名作が全面改稿を経ていま甦る。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kawa
37
幕末日本と開国を迫った諸外国外交官・商人との通貨戦争を描く。主人公は官僚・水野忠徳、英国外交官オルコック、米国外交官・ハリス。実は通貨の仕組みが面倒で以前に中途挫折。今回は最近読了吉村昭「落日の宴 勘定奉行川路聖謨」での川路の部下が水野と言う関係もありスムーズに没入読了。通貨の仕組みの理解は今回も苦戦だったが、幕末動乱を経済的側面から観察でき手に取って良かった作品。水野以外の幕末官僚の無能ぶりも際立つが、それ以上にオルコック・ハリスの悪辣ぶりに腹が立つ。彼らから見れば幕末日本はゴールドラッシュの国だった。2023/03/25
ちゃこ
8
第4回(1985年)新田次郎文学賞。[1984年講談社刊行版、1991年講談社インターナショナル英訳刊行版を全面改稿─あとがきにて、作者が改稿までの経緯についても述べている] 1859年(安政6年)3月〜。幕末に相次いで調印された通商条約による開港と、それによって起きた貨幣問題(交換比率の問題、小判の流出と急激なインフレなど)を英国公使オールコックと米国公使ハリスの視点から描いた作品。 後に佐藤氏が書いた『覚悟の人―小栗上野介忠順伝』では、(続→)2014/03/26
えちぜんや よーた
8
元禄期の勘定奉行・荻原重秀は天才的な財政家のようです。「官符の印」理論→「支払い能力について信用のある政府が裏書きしていれば、たとえ瓦やがれきであっても、通貨となる」。現代の管理通貨理論のはしり。たしかに1万円札の「原価」は20円ぐらいと聞きます。2012/05/19
hanagon44
7
金含有量比較で1小判=4ドル。1小判=4イチブだから1ドル=1イチブ。日本側のまともな役人の主張を,イチブ貨は重さで1ドルの1/3で日本政府の刻印により3倍の価値を持つことはあり得ないと傲慢に退け,1ドル=3イチブにせよと脅した西洋人達。国際標準レートの金銀比価1対16,日本国内1対5を悪用し,ドル→イチブ→小判として3倍の儲けで日本を食い物にした厚顔無恥ぶりに絶句。国際社会では相手の善意に頼らず自分たちの主張を貫かなくては踏み付けにされるだけという教訓は今にも通じることだと思う。お花畑外交は奴隷への道。2015/09/26
Hiroki Nishizumi
3
参考になった。幕末の金銀不均衡について歴史的経緯が少し分かった。オールコックについてさらに調べたくなった。2018/06/19
-

- 電子書籍
- ふたりソロキャンプ(2)
-
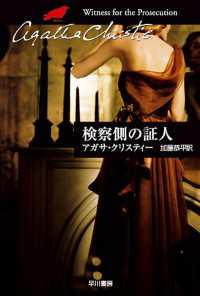
- 電子書籍
- 検察側の証人 クリスティー文庫