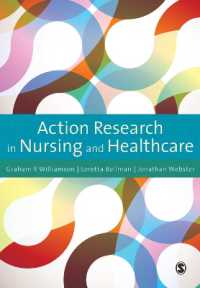出版社内容情報
ネット怪談はどのように発生し、伝播するのか。きさらぎ駅、くねくね、リミナルスペース……ネット民たちを震え上がらせた怪異の数々を「共同構築」「異界」「オステンション(やってみた)」など民俗学の概念から精緻に分析、「恐怖」の最新形を明らかにする
内容説明
「きさらぎ駅」「くねくね」「三回見ると死ぬ絵」「ひとりかくれんぼ」「リミナルスペース」など、インターネット上で生まれ、匿名掲示板の住人やSNSユーザーを震え上がらせてきた怪異の数々。本書ではそれらネット怪談を「民俗(民間伝承)」の一種としてとらえ、その生態系を描き出す。不特定多数の参加者による「共同構築」、テクノロジーの進歩とともに変容する「オステンション(やってみた)」行為、私たちの世界と断絶した「異世界」への想像力…。恐怖という原始の感情、その最新形がここにある。
目次
第1章 ネット怪談と民俗学
第2章 共同構築の過程を追う
第3章 異世界に行く方法
第4章 ネット怪談の生態系―掲示板文化の変遷と再媒介化
第5章 目で見る恐怖―画像怪談と動画配信
第6章 アナログとAI―二〇二〇年代のネット怪談
著者等紹介
廣田龍平[ヒロタリュウヘイ]
1983年生まれ。法政大学ほか非常勤講師。専攻は文化人類学、民俗学。博士(文学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
220
インターネットに現れた数々の怪談は、新しいメディアだけに生まれた経緯や成長プロセスが把握しやすい。そんなネット怪談を民俗学の専門家が分析すると、人はなぜ恐怖を求め怪談を作っていくのかが見えてくる。科学の恩恵あればこそのネットやスマホ内で得体の知れない話題が語られ、科学では説明がつかないからこそ人は魅せられ面白がるのだ。そんな面白がる人が勝手に集まって、様々な怪談を共同構築していく。AI技術の進歩が加わると、今後は人を介さず自律的に発展する可能性が出てくる。それこそどんな創作より恐ろしい事実かもしれないが。2025/04/18
kinkin
135
ネット怪談を民俗学的に考察する本。民俗学がいまだにどのような学問であるかを理解していない。民俗学というのは間口がとても広い学問と聞いたことがある。民俗学の中でも新しい分野なのだろう。読んでいて感じたのは出てくる怪談話についてほとんど知らない著者はネットに載っている話について、いろいろと解説されている。なるほどそんな話なのかを知ることが出来た。しかし民俗学的な研究なら、ネット内の怪談について話に出てくる何とか村を探したりや、噂についてのネット民とのやりとりなどの、攻めの検証があってもよかったと思った。 2024/11/17
☆よいこ
102
分類388。ネット怪談について、その黎明期から現代までを年代順に分類収集した論文。とても分かりやすい▽[第1章:ネット怪談と民俗学]きさらぎ駅/スレンダーマン/平成令和怪談略史[第2章:共同構築の過程を追う]2ちゃんねる[第3章:異世界に行く方法]現実感のありか[第4章:ネット怪談の生態系]怪談サイト/海外の状況/ネット老人会[第5章:目で見る恐怖]画像怪談と動画配信/クリックベイト/逆光的オステンション[第6章:アナログとAI]バックルーム▽参考文献、怪談索引あり。良アーカイブ。2024年発行2025/06/06
nonpono
100
怖い話は苦手だが興味がないわけではない。こっくりさんの不思議さに驚き心霊写真に怖くなり、みんなで怪談話をしていたから。本書はインターネット上の怪談の歴史、民俗学である。わたしが2ちゃんねるのプロレスの板をよく読んでいた時代に、様々なオカルトな板があったんですね。2ちゃんねる特有の匿名性やネタ気質がまた発展を助けています。また機械の進化。周囲に霊がいると光ったり声が出る機械は知りませんでした。カメラとARアプリも。これからもっとハード面で進化すると思いますが、そうなるとまた話す怪談の怖さが際立ったりして。2025/08/05
yukaring
93
「きさらぎ駅」や「くねくね」などネット上の不特定多数により構築されていく怪談や画像から生まれ広がった「スレンダーマン」など怪談がどのように確立され、拡散していくのかなどが学問として取り上げられているのが興味深い。2ちゃんねるを使った「異世界へ迷い込んだ系」の実況型怪談の誕生や別のスレへ連鎖していく連鎖型怪談、狭い土地に伝わる因習系怪談の進化など、分類と系譜が実際の怪談を紹介しながら語られるのも面白い。「コトリバコ」や「ひとりかくれんぼ」「ヒサルキ」なと知らない怪談も多数語られていてとても楽しめた。2025/02/22