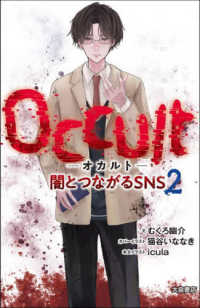出版社内容情報
アメリカで薬物の過剰摂取による死亡者が増えている。厳しい取り締まりで防げないのはなぜか。社会の分断と依存の関係を丹念に検証。アメリカで薬物の過剰摂取による死亡者が増え続けている。厳しい取り締まりで防げないのはなぜか。薬物の人体への影響を調査し、さらに貧困や人種差別などの社会の分断と依存の関係を丹念に検証。「人生を棒に振る」ことを強いるのは薬物か、社会の不公正か。
カール・ハート[ハート カール]
寺町 朋子[テラマチ トモコ]
内容説明
「薬物常用者」とされるアメリカ人は2000万人にものぼり、過剰摂取による死亡者が増えつづけている。有効な対策にならない薬物政策はどこから生まれたのか。神経科学者が規制の歴史をたどり、薬物が人体にもたらす影響を実証することで、従来の依存のイメージを問いなおす。なぜ科学的な裏づけのない政策がまかり通るのか。この政策の犠牲者はだれなのか。マイアミの貧困地区から身を起こし、アフリカ系アメリカ人として初めてコロンビア大学の自然科学系終身教授についた著者が、自らの人生をかけて告発する。PEN/E・O・ウィルソン科学文芸賞を受賞し、“ニューヨーク・タイムズ”紙や“ボストン・グローブ”紙などで絶賛された科学啓蒙書。
目次
私の出自
あの前とあと
ビッグママ
性教育
ラップと報酬
薬物と銃
選択とチャンス
基本軍事訓練
「家庭とは憎しみがあるところ」
迷路
ワイオミング州
いまだに単なる一人の黒んぼ
実験参加者の行動
胸を突く出来事
新たなクラック
救いを求めて
虚構ではなく事実にもとづいた薬物政策
著者等紹介
ハート,カール[ハート,カール] [Hart,Carl]
コロンビア大学心理学科長。フロリダ州マイアミで生まれ、メリーランド大学で心理学の学士号を、ワイオミング大学で実験心理学と神経科学の修士号と博士号を取得する。神経精神薬理学の分野で数々の論文を発表するほか、薬物と社会と人間の行動に関する教科書を執筆する。2014年、『ドラッグと分断社会アメリカ―神経科学者が語る「依存」の構造』でPEN/E.O.ウィルソン科学文芸賞を受賞
寺町朋子[テラマチトモコ]
翻訳家。京都大学薬学部卒業。企業で医薬品の研究開発に携わり、科学書出版社勤務を経て現在に至る。訳書多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
どんぐり
くさてる
白玉あずき
ステビア
BLACK無糖好き