内容説明
伝えたいのは、「進化は進歩ではない」こと。つねに変化し、新しく生まれ変わる進化生物学の現在をあますところなく語る。生物の多様性を礼賛するグールドの科学エッセイ。
目次
第5部 博物館賛歌(恐竜ブーム;キャビネット博物館―新鮮採れたてだよー! ほか)
第6部 優生学のばらばらな顔(種なしプラムは考える葦の教訓となるか;優生学を裏付ける証拠の吸い殻 ほか)
第7部 進化の理論、進化の物語(ダーウィンの革命は成就させられるか;どでかいキノコ ほか)
第8部 リンネとダーウィンの祖父(自然の仮面をはじめて剥ぐ;つぼみとたっぷりの性生活によって自然を配置する ほか)
1 ~ 1件/全1件
- 評価
COSMOS本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
魔魔男爵
5
桂冠詩人テニスンホモ疑惑GETだぜ!グールドの公正明大さが理解出来る良書。キリスト教会に支配された暗黒の中世時代には、地球は平らであったと、皆信じていた説を反駁してます。宗教人を貶める為の科学教信者の陰謀だったのだ!科学者なのに科学と宗教が両立すると思っているグールドは人が善すぎる。科学教信者の私は、愚かな宗教人は鏖殺すべきと思いますw。サー・ロナルド・エイルマー・フィッシャー(1890-1962)では無くて、ヨハン・ゴットへルフ・フィッシャー・フォン・ヴァルトハイム(1771-1853)の方のフイッシャ2017/05/03
印度 洋一郎
3
科学エッセイの名手のエッセイ集七冊目の下巻。お題は「博物館」「優生学」「進化論」などで、やはり著者のホームグラウンドの進化論に関する文章に熱が篭っている。時代を感じるのは、執筆当時公開された「ジュラシック・パーク(一作目)」に関する、「商業主義が科学の大衆への啓蒙を歪める」という苦言。その他、「巨大な地衣類は、地上最大の生物か?」という疑問から「個体とは何か?」という考察に行き着くのも興味深い。動物と植物では、個体に関する概念が違うらしい。へ~。そして、「地球上の生物は今尚ほとんど未発見のまま」という話も2019/12/25
kinaba
2
2014年の今から見て読むと、だいぶ、著者らを始めとする人々の啓蒙活動は功を奏しているんじゃないかと思える。(チンパンジーとヒトを最近傍としてグループ分けする考え方とか、少なくとも今の日本で違和感はなく受け入れられているんじゃないかと。)興味深い2014/11/02
NAGIA
1
進化というものを我々は誤解している、ということをすでに知っていたが、それでも認識を変えるのは難しい。日本語の「進化」という単語がすでに誤解を誘発する言葉なんだよなあ。単純な生物から徐々に複雑化して、人間が生物界の頂点、みたいな思い込みは、なかなか完全に消し去ることができない。また、優生学というものの恐ろしさを、ナチスを例にとって(最凶の例)訴えている。誤った疑似科学に踊らされやすい文系一般大衆代表として、気をつけなきゃなと思う。科学を統制する倫理は我々の方にむしろ委ねられている。2013/11/01
-
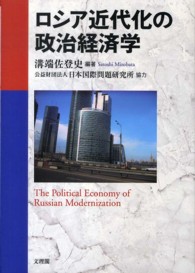
- 和書
- ロシア近代化の政治経済学
-

- 和書
- な~るほど!の現代物理







