内容説明
「腹が立つ」なら腹で、「頭に来る」なら頭で怒る。では「むかつく」の場合はどこで怒っているのか?「肌を許す」とか「お肌の曲がり角」とは言っても、「皮を許す」とも「お皮の曲がり角」とも言わないのはなぜか?…日本人が無意識に抱いている身体観をはらんだ、「からだ」に関わることばを用いた言い回しに注目するというユニークな手法により、近代・現代の日本人像を浮かびあがらせる快作。
目次
からだことばが消えていく
「腹がたつ」「頭にくる」「むかつく」
「腹」と「胸」、神経とストレス
「気」と「息」、からだといのち
「肌感覚」と「皮感覚」
「肩」の心性史
「足」の文化、「腰」の文化
見る、視る、観る、診る、看る
聞く、聴く、訊く、効く、利く
ふれる、なでる、抱く、包む
ピアノをひく、風邪をひく、汗がひく
「からだ」「肉体」、そして「身体」
身のこなし、身にしみる、身をまかす
「気持ちいい」行きかた
「疲れ」社会、「痛み」人生
ことばの治癒力
作家とからだとことば
著者等紹介
立川昭二[タツカワショウジ]
1927年、東京生まれ。早稲田大学文学部史学科卒業。北里大学名誉教授。歴史家。とりわけ文化史、心性史の視点から、病気や医療について研究する。『歴史紀行・死の風景』でサントリー学芸賞受賞
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
AR読書記録
3
トリビア的に面白い。そして、言葉によって定着する、また言葉が失われることで感じ取れなくなる感覚がある、そういう関係性も深く納得させられる。“昔は豊かで、それが失われた今は貧しい”みたいな話であれば、いや今はまた違う新たなものが獲得されていているのだよご老人...という気になるけれど、そんな説教臭さを感じるほどでもなく。おまけ的な、からだことばから作家と作品を分析する「作家とからだことば」も短いながら興味深く、うん、失礼ながらハヤカワ文庫NFに期待してるレベルよりはるかによかった。2015/08/09
しょ~や
0
からだことばって改めて考えると無数にありますね。筆者が学生に問うたという「○○という語句を含む言葉を挙げよ」という問いを自分でも考えてみるが、思った以上に出てこない。言われれば分かるし使ってる言葉もあれば、意味はなんとなく分かるという程度のものも。長く使われてかつての様子を伝える言葉が失われていくことが少し寂しいと感じた。2015/10/08
ありんこ
0
からだことばから、体にまつわる歴史や文化を探っていきます。体にまつわる言葉がこんなにたくさんあること、そしてその言葉を最近は使わなくなってきている理由、背景。昔の文芸作品に登場するからだことばの数々と表現力の豊かさに驚かされます。頭を使いすぎる現代人は、もっと心やからだをいっぱい使うこと。全身でいろんなことを体験すること。とても大事なことを教わった気がしました。2009/10/02
-
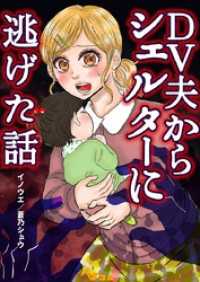
- 電子書籍
- DV夫からシェルターに逃げた話42 V…
-

- 電子書籍
- 漫画的展開で彼をオトしたい!(2)
-
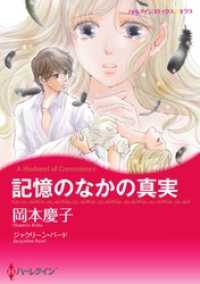
- 電子書籍
- 記憶のなかの真実【分冊】 9巻 ハーレ…
-
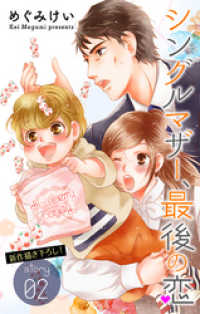
- 電子書籍
- Love Silky シングルマザー、…
-

- 電子書籍
- AneLaLa ヒノコ story04…




