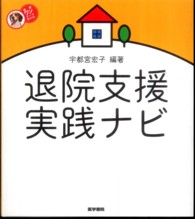内容説明
1909年、カナダで5億年前の不思議な化石小動物群が発見された。当初、節足動物と思われたその奇妙奇天烈、妙ちくりんな生きものたちはしかし、既存の分類体系のどこにも収まらず、しかもわれわれが抱く生物進化観に全面的な見直しを迫るものだった…100点以上の珍しい図版を駆使して化石発見と解釈にまつわる緊迫のドラマを再現し、歴史の偶発性と生命の素晴らしさを謳いあげる、進化生物学の旗手グールドの代表作。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
COSMOS本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mae.dat
231
カンブリアは爆発だっ! ずっといつか読まなきゃ(使命感)と、思ったまま心の積読本になっていましたが、漸く読みました。時が経ってしまってる部分はしょうがなく。冥王代に終止符を打ち、顕生代幕開けです。顕生生物が現れて間も無い事ですから、多様性に乏しいのは致し方ないのかも。然し乍らボディープラン(=門)は出揃っている。異質性には富んでいるのがワンダフル! 軟体性生物をも含むバージェス頁岩と言う地球さんからの贈り物がワンダフル! そしてその造形がワンダフル! なのですかね。地球と言うのは進化の実験場なのかなぁ。2022/11/09
Nobu A
36
HONZ推薦本。00年刊行。購入して書架で埃を被って数年は鎮座していた本書。つくづく成毛眞著書「面白い本」や「決定版-HONZが選んだノンフィクション」はヤバいなと思う。読んだら読みたい本が蛆虫の様に増殖。そして読書量が追い付かずこんなオチが付く。中生代の恐竜も魅力的だが、バージェス頁岩の生物も不思議な物体。個々のイラストが挿入され、目の前に現れたらさぞ仰天するだろうな。正直どれも気持ち悪い。そもそも毛虫や蛾が嫌いな人間には拒絶反応しか起きない。ただイラストを見る分は問題ない。ざっと流し読み読了。2024/07/27
たかしくん。
34
再読ですが、前回はチンプンカンプンでした。今回はこの本の面白さを、相当楽しんだと思います。「アノマリカリス」やら「オパビニア」やら、奇妙奇天烈なバージェス頁岩の動物群とその後のカンブリアの大爆発を通して、更に新しい生物進化の見方を提言したグールドの存在感を感じ取りました。話も面白く、途中で色々と寄り道するところもまたいい!氏の考え方は、現在では一部否定されている面もありますが、それは割り引いてもこの本は「フェルマーの最終定理」に近い面白さを兼ね備えてますね。2015/04/05
かんやん
22
5億数千年前のカンブリア紀の生命の爆発的増加、そこで生まれた奇妙奇天烈な生物たち。しかし、化石の発見者がそれらを節足動物門に分類してしまったのは、なぜなのか。個々の生物を解剖学的に取り上げると、ほとんどが既知の分類をはみ出してしまうのに。そこから、著者はハシゴ段的、逆円錐状の進化観(生命の系統樹に表されるような、単純なものから複雑・多様なものへの進化)の見直しを進めてゆく。優れて適応したものが生き残るのではなく、偶然が支配するランダムな世界。壮大な仮説の是非はともかく、復元された奇妙な生物たちが楽しい。2017/12/16
きゃれら
21
グールドは複数読んでいるはずだが、本書は浩瀚に恐れをなして初読。アイシュアイア、シドネイア、ナラオイアなどの名前は覚えていた。その後間違いがわかったこともあって、ライバル(?)ドーキンスに大きく水をあけられているが、ぼくは面白く読んだし、読むべき内容を含んでいると思った。科学者といえども先入観に囚われて見えないものがあること、実験室の中のようなエビデンスがないことが価値が低いことにはならないことなどが著者の主張のベースにある考え方で、細かいエピソードの積み重ねが説得力を持たせている。だから浩瀚なのだ。2024/06/22