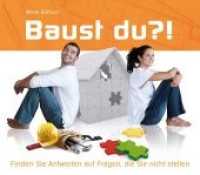出版社内容情報
「古代文明」を見つめることで、今この世界の見方が変わる?!
世界史、江戸時代に続く「3か月でマスターする」歴史編の第3弾は、近年、新事実が次々と明らかになる「古代文明」。これまで西洋近代の視点からの解明が主流だった考古学の世界でも、21世紀の脱・西洋中心歴史観の潮流の中で、これまで常識とされてきたことが次々と覆されている。
そんな新潮流を、全12回、12か所の文明を取り上げ、時代、場所ともに壮大なスケールで紹介する3か月シリーズ。1冊目では、「文明の始まり」「メソポタミア」「ヒッタイト」「エジプト」について取り上げる。
謎めいた雰囲気やロマンといった憧れの対象としての「古代文明」鑑賞に留まらず、今の時代にも響く、“人間が多様な地域で生きる手法”や、それぞれの“文明の知恵”にもフォーカスし、“なぜ古代文明を見つめるのか”という視点を大切にしながら、現代を考えるヒントを提案する。
第1回:衝撃!最古の巨大遺跡 見直される“文明の始まり”
ゲスト研究者:三宅 裕
文明は農耕の発達とともに大河の流域で生まれた…。その定説を大きく揺るがす衝撃の遺跡がトルコ東部、川のない丘の上で発掘された。「ギョベックリ・テペ」で読み解き直される“文明の始まり”についてと共に、シリーズ全体のガイダンスも。
第2回:メソポタミア 都市は“最終手段”だった?
ゲスト研究者:常木 晃
小麦の灌漑農業の発展で、都市や都市国家を最初に築いたのは南メソポタミア、BC3500年頃にウルやウルク(現イラク南部)が形成された…。が定説だったが、最新調査では、BC4200年頃に北メソポタミアに最初の都市があったことが判明。都市をめぐる新たな視点からメソポタミアを読み解き直す。
第3回:ヒッタイト 過酷な大地の帝国の秘密
ゲスト研究者:津本 英利
西アジアで新たな発見があいつぐのがヒッタイト。鉄器と戦車を操る好戦的なイメージが強いが、都のハットゥシャの発掘や膨大な粘土板の解読から、まったく違う姿が浮き彫りとなった。 “限られた恵み”を大切に徹底的に生かす、という新たなヒッタイトのイメージを紹介。
第4回:エジプト ピラミッドと黄金が社会を変えた
ゲスト研究者:河合 望
メソポタミアから農耕を導入後、独自の発展をとげたエジプト。近年の研究で、ピラミッドと黄金が発展と衰退のカギを握ったことが明らかに。王権の象徴だった金がエジプトで採れなくなり、過去の王の墓を暴いて黄金を入手するほどだった。輝きを得られなくなった王の権威は失墜していった。ピラミッドと黄金で読み解くエジプトの栄枯盛衰。
【目次】
第1回:衝撃!最古の巨大遺跡 見直される“文明の始まり”
ゲスト研究者:三宅 裕
文明は農耕の発達とともに大河の流域で生まれた…。その定説を大きく揺るがす衝撃の遺跡がトルコ東部、川のない丘の上で発掘された。「ギョベックリ・テペ」で読み解き直される“文明の始まり”について紹介すると共に、シリーズ全体を貫く「古代文明」の見方、その新たな視点について解説。
第2回:メソポタミア 都市は“最終手段”だった?
ゲスト研究者:常木 晃
小麦の灌がい農業の発展で、都市や都市国家を最初に築いたのは南メソポタミアで、BC3500年頃にウルやウルク(現イラク南部)が形成された…。が定説だったが、最新調査では、BC4200年頃に北メソポタミアに最初の都市があったことが判明。都市をめぐる新たな視点から「メソポタミア」を読み解く。
第3回:ヒッタイト 過酷な大地の帝国の秘密
ゲスト研究者:津本 英利
西アジアで新たな発見があいついでいる「ヒッタイト」。鉄器と戦車を操る好戦的なイメージが強いが、都であったハットゥシャの発掘や膨大な粘土板の解読から、まったく違う姿が浮き彫りとなった。 “限られた恵み”を大切に徹底的に生かす、という新たなヒッタイトのイメージを紹介。
第4回:エジプト ピラミッドと黄金が社会を変えた
ゲスト研究者:河合 望
メソポタミアから農耕を導入後、独自の発展をとげた「エジプト」。近年の研究で、ピラミッドと黄金が発展と衰退のカギを握ったことが明らかに。王権の象徴だった金がエジプトで採れなくなり、輝きを得られなくなった王の権威は失墜していった。ピラミッドと黄金で読み解くエジプトの栄枯盛衰。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
まえぞう
にしがき
倉屋敷??
三河のだら
ちかこ