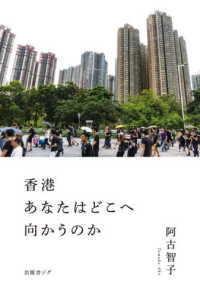出版社内容情報
カーターやオバマの失敗、ビル・クリントンの成功を精密かつ躍動的に描いて、大統領を悩ませる「期待と現実のギャップ」を浮き彫りにする。トランプにもヒラリーにも有効な革新的視点を打ち出す。
内容説明
アメリカの大統領は世界的な注目を集めて就任するが、任期途中で失速することも多い。オバマもそうだった。なぜか。日本やイギリスの首相とは違って、大統領には自由に政策を実現するだけの権限が与えられていないからだ。本書はイギリス植民地以来の歴史と国際比較から、大統領の権限が弱い理由を解明し、カーター、ビル・クリントン、オバマらを分析して、各大統領がこの困難にどう取り組んできたのかを明らかにする。一貫した視点で根本問題から将来像までを見通す、アメリカ政治の正確な理解に欠かせない一冊。
目次
第1章 大統領制の誕生
第2章 現代大統領制のディレンマ
第3章 ディレンマを考える視点
第4章 新大統領に何ができるか
第5章 議会多数党の交代を何をもたらすか
第6章 アメリカ大統領制の未来
著者等紹介
待鳥聡史[マチドリサトシ]
1971年生まれ。京都大学大学院法学研究科教授。専攻は比較政治論。京都大学博士(法学)。著書は『首相政治の制度分析』(千倉書房、サントリー学芸賞)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ばんだねいっぺい
29
アメリカ大統領制の生まれた経緯とその特徴について トランプ大統領は、「大統領は提唱した政策を思ったほど実現できるわけではない。」という「現代大統領制のディレンマ」を乗り越えられるのだろうか。乗り越えられなきゃいいなぁ。2016/12/22
yokmin
17
副題「権限の弱さをどう乗り越えるか 」の通りである。そこにオバマの苦悩があった。トランプも同じような経験をするであろう。いや、ぜひ経験してほしい。そこで、政権を投げ出すか、それとも弾劾に進むか、見ものである。権力は「安倍首相>トランプ大統領」という図式が興味深い。2016/11/24
koji
13
トランプ大統領誕生のタイミングで読みました。アメリカにおける現代大統領制のディレンマ(多数派の行き過ぎを抑止することが想定されていた制度構造のままで、多数派の期待を担うという役割)を主題に、現代の大統領がどのように権限の弱さを克服しようとしたかを解明します。多数の文献を渉猟し論点をきちんと整理して持論を展開しており読みやすい好著になっています。とりわけ第4章「新大統領に何ができるか」の「変革を訴えながら明暗がわかれたクリントン(明)とカーター(暗)」はトランプ変革の成否の鍵ともなるもので参考になりました。2017/03/01
あんころもち
12
本書はアメリカ大統領の弱さを前提として、いかなる場合において大統領が指導力を発揮していくかについて、「ハネムーン期間は法案を通過させやすい」といった通説をもとに、事例研究、統計的手法の双方を用いて考えていく。用いる手法も章によってさまざまであるため、政治研究の幅広さを味わえる一冊になっている。 何より、アメリカ政治を勉強する身としては注が本当に詳細でその後の読書が捗る。 これで1400円なので本当に買い。2016/12/30
(k・o・n)b
6
議会を抑制する存在として制度設計された米国の大統領。前世紀からはリーダーシップ発揮を期待されつつも、憲法上・政権政党内での権限が弱く、思うように政策を進められない(現代大統領制のジレンマ)。更に近年は二大政党の凝集性が高まり、分割政府下で行き詰まることも多い。両政党と距離を取り超党派での合意形成を進めたクリントンと、党派性を打ち出したオバマの対比が興味深かった。確かにトランプは分断を生んだが、イデオロギーの分極化はずっと以前から起こっており、ある意味その帰結としてのトランプ政権とも言えるのかも、と思った。2020/12/03