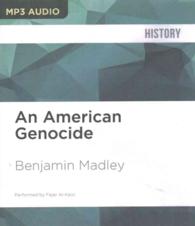出版社内容情報
哲学者たちは何と向き合ってきたか?
日本における哲学の第一人者が集結し、全3巻で西洋哲学史の大きな見取り図を示す! 今回は、デカルトからドイツ観念論までの近代哲学。時代のうねりのなかで、人間の知性の働きを突き詰めた哲学者たちの思索に迫る。決定版の入門シリーズ第2弾!
内容説明
哲学研究の第一人者が集結し、西洋哲学史の大きな見取り図を示すシリーズの第二弾!本巻では、デカルトからカント、そしてヘーゲルを中心としたドイツ観念論までの近代哲学を扱う。時代のうねりのなかで、哲学者たちは「人間の知性」といかに向き合ってきたか。思索の核心と軌跡を浮き彫りにする。教養としての哲学のあり方をめぐる特別章も収載した、決定版の入門書!
目次
第1章 転換点としての一七世紀―デカルト、ホッブズ、スピノザ、ライプニッツの哲学(イントロダクション「いきなり始める」哲学;転換点としての一七世紀)
第2章 イギリス哲学者たちの挑戦―経験論とは何か(イントロダクション イギリス経験論トリオ+1;イギリス哲学者たちの挑戦)
第3章 カント哲学―「三批判書」を読み解く(イントロダクション 人間的「自由」のための哲学;カント哲学)
第4章 ドイツ観念論とヘーゲル―矛盾との格闘(イントロダクション 哲学史上、稀に見る濃密な時代;ドイツ観念論とヘーゲル)
特別章 哲学史は何の役に立つのか(哲学史から何を学ぶか;「神」という説明原理 ほか)
著者等紹介
斎藤哲也[サイトウテツヤ]
1971年生まれ。人文ライター。東京大学文学部哲学科卒業。人文思想系を中心に、知の橋渡しとなる書籍の編集・構成を数多く手がける
上野修[ウエノオサム]
1951年生まれ。大阪大学名誉教授。専門はスピノザ、デカルトなどの西洋近世哲学、哲学史
戸田剛文[トダタケフミ]
1973年生まれ。京都大学大学院教授。専門は知覚理論、認識論、ジョージ・バークリ
御子柴善之[ミコシバヨシユキ]
1961年生まれ。早稲田大学文学学術院教授。専門はカントを中心とした西洋近現代哲学、倫理学
大河内泰樹[オオコウチタイジュ]
1973年生まれ。京都大学大学院教授。専門はヘーゲルを中心とするドイツ観念、批判理論、ネオ・プラグマティズムなど
山本貴光[ヤマモトタカミツ]
1971年生まれ。文筆家・ゲーム作家。著書『文体の科学』(新潮社)、『「百学連環」を読む』(三省堂)、『文学のエコロジー』(講談社)など
吉川浩満[ヨシカワヒロミツ]
1972年生まれ。文筆家・編集者。著書『理不尽な進化』『人間の解剖はサルの解剖のための鍵である』(ちくま文庫)、『哲学の門前』(紀伊國屋書店)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ころこ
特盛
まさにい
原玉幸子
かふ
-
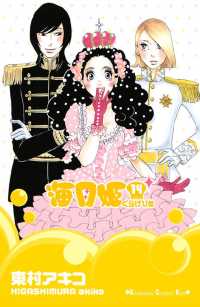
- 電子書籍
- 海月姫(14)