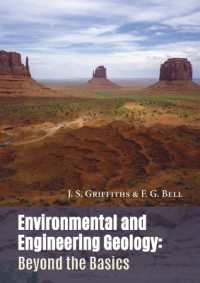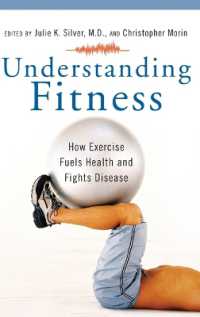内容説明
引きこもる小学生。算数のできない大学生。他人と会話できず、すぐにキレてしまう若者。彼らの「冷えた身体」を暖め、「生きる力」を鍛えるために必要な「三つの力」を、教育学の俊英が、授業実践に基づき提言する。高い関心を集める「斎藤メソッド」の試みを紹介しながら、子どもたちのアイデンティティをどう育てるのか、レスポンスできる「動ける身体」をどう作るのかを考える。自信を失った日本と日本人に活を入れる、注目の書。
目次
「生きる力」とは何か―真の基礎力を求めて
三つの力(コメント力(要約力・質問力)
段取り力
まねる盗む力)
存在証明=アイデンティティの教育
クリエイティブな関係・場を作る技
「斎藤メソッド」の試み
著者等紹介
斎藤孝[サイトウタカシ]
1960年、静岡生まれ。東京大学法学部卒業。同大学大学院教育学研究科学校教育学専攻博士課程修了。現在、明治大学文学部助教授。専攻は教育学・身体論。教職課程で中高教員の養成に従事
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Bun-ichi Kawamoto
12
コメント力、段取り力、まねる盗む力。斎藤先生が明治の助教授だったときの本だが、今でもこの原点の考えは変わっていない。2016/09/24
なつ
8
ずっと読みたいと思って探していた本です。幼児教育を学んでいて、生きる力とはなんぞやと思い読んでみました。斎藤さんなりの生きる力が集約されていて、自分自身省みるいい機会になりました。もう少し生きる力について模索していきます。2013/06/24
Michi
5
子どもに伝える前に大人が実践したい、三つの力。伝えたい三つの力とは、1.コメント力(要約力、質問力)2.段取り力、3.まねる盗む力。リマインド〜クリエィティブな関係・場を作る技➡︎レスポンスする身体、冷えた身体を暖める➡︎コミュニケーションを増幅するため不可欠なのはレスポンスする体である。タイミング良くレスポンスされるとコミニケーションはうねりを増すように増幅してくる。2014/01/26
ねっしー
4
この本での生きる力は、コメント力、段取り力、まねる盗む力。私には圧倒的に足りない。数式を書くことは要約力の極みであり、図式⇔言語を行き来することで教科の壁をなくす。総合学習が始まったばかりの頃の本だが、今でも十分通じる。教師を目指す人でなくても、この本は楽しんで読める。ぜひ再読したい。2014/02/18
ざきさん
3
数多く本を執筆されている斎藤孝先生の中で一番好きな本。タイトルの三つの力は「コメント力、段取り力、まねる盗む力」書店に並ぶビジネス書の殆どがこの『三つの力』のどれかの本ではないだろうか。さらに内容ではメモの重要性、アイデンティティー教育、クリエイティブな場を作る技などもう盛り沢山!そして印象的なのは『冷えた体』への警笛。本が出版されてから20年、今も教育に携わる斎藤孝先生は今も子供たちは冷えていると感じているのか、それとも良い方向に向かっているのか。いつか会えたら聞いてみたい。冷めてなんかいないと信じたい2021/01/19