内容説明
言葉はなぜかわるのか。人間活動の所産であることはもちろんだが、巨視的にみれば、自然環境が重要である。なぜなら、気候の変動によって民族移動が起こり、それが言葉の変化をもたらし、ひいては現在の世界の言語分布にいたっているからだ。本書は、地理学の碩学が言語年代学の成果をふまえながら、気候と言語のダイナミックな関連性を一万年の人類史の中で実証するという野心的試みである。
目次
第1部 気候と言語(基礎単語の分布が意味するもの;インド・ヨーロッパ諸語の分布はどうして成立したか;アフリカ諸言語の移動;広大な地域にわたるマライ・ポリネシア諸語;アメリカ大陸の諸語;ウラル・アルタイ諸語;日本語とその周辺)
第2部 気候変化と人間の変動(氷河期から高温時代へ;寒冷化がはじまる;3500年前の危機;鉄器扇代初期の寒期;紀元前後の暖期;民族移動の寒期;リトルオプチマム期;リトルアイスエイジ期;現暖期;世界の前線帯)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ハイパー毛玉クリエイター⊿
1
何千年、何万年スパンでの気候変動が、人類の言語分布にどのような影響を与えたのかを考察するという本。気候変動による人々の移動が各地の言語の変化に関わってくるというのはまあ確かに想像のつく話ではあるんだけど、現代においても、人間の移動のみならず、文化交流の結果として、遠く離れた国にぽつりぽつりと全くちがう語族の単語が紛れ込んで定着しているということもあるので(特に名詞では多そうだ)、一概に「気候変化→民族の移動→言語の変化」という図式は成り立たないんだろうなぁとも思う。2016/08/19
takao
0
寒冷化による南方移動で今の言語分布に2016/08/13
-

- 電子書籍
- シリアルキラー異世界に降り立つ 連載版…
-

- 電子書籍
- 毒虫魔王~虫たちの戦争~【タテヨミ】第…
-
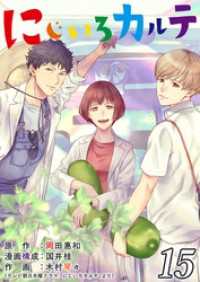
- 電子書籍
- にじいろカルテ【単話】 15 Rent…
-
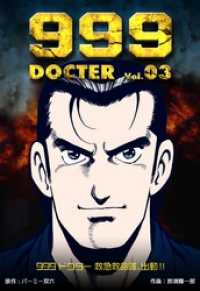
- 電子書籍
- 999ドクター~救急救命隊、出動!!3…
-
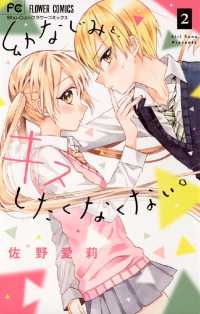
- 電子書籍
- 幼なじみと、キスしたくなくない。(2)…




