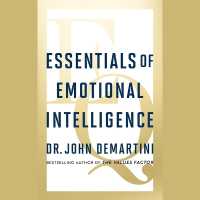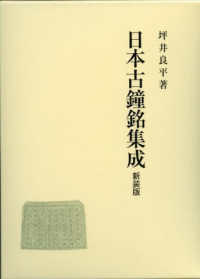出版社内容情報
科学技術と社会,研究者と市民の間を「つなぎ」,学問分野や組織の壁を「こえ」,課題を解決し,今後の問題を防ぐために,STSはどう「動く」のか.科学計量学や質的調査,市民ワークショップの手法などさまざまな方法論について,具体例を交えながら紹介する.
内容説明
さまざまな学問が交差し、STSを作り上げる。科学技術と社会、研究者と市民の間を「つなぎ」、学問分野や組織の壁を「こえ」、課題を解決し、今後の問題を防ぐために、STSはどう「動く」のか。具体例を交え、さまざまな方法論を紹介する。刺激に満ちたシリーズ全3巻完結。
目次
第1章 科学計量学
第2章 先端科学技術の質的研究法
第3章 ラボラトリー・スタディーズ
第4章 市民参加型ワークショップの設計
第5章 科学技術の人類学―多様化する「科学技術の民族誌」
第6章 科学史とSTSの接点
第7章 科学哲学の方法
第8章 技術哲学と技術者倫理
第9章 科学社会学の方法
第10章 言葉とモノ―STSの基礎理論
著者等紹介
藤垣裕子[フジガキユウコ]
東京大学大学院総合文化研究科教授
小林傳司[コバヤシタダシ]
大阪大学名誉教授・JST社会技術研究開発センター上席フェロー
塚原修一[ツカハラシュウイチ]
関西国際大学教育学部客員教授
平田光司[ヒラタコウジ]
高エネルギー加速器研究機構特別教授
中島秀人[ナカジマヒデト]
東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
無重力蜜柑
8
1巻は読んだが2巻より面白そうだったので先にこちら。方法論別に全10章という感じだが1巻との違いは曖昧。ガチガチの量的研究からいかにも人文系なテクスト批判まで多様。STSの本当に最先端の議論が総覧できるのが良い。以下章別に。「科学計量学」:引用分析やIFなどを用いたまさに量的メタ科学。米国の科学政策に合わせてデータ構築からモデル構築へと進んだこと、IFや大学ランキングなどの分野内概念が科学者も含む素人に誤解、乱用されていることなど。残念ながら日本ではほぼ機能してない分野と思われる,2022/07/06
mashi
0
個々のトピックについてもう少し具体的なことを知りたかったな。2021/01/16