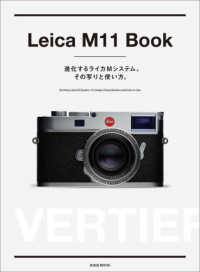出版社内容情報
ミステリアスな生態を追う――かつて「海のギャング」といわれたシャチは、すばらしい文化をもつ魅力的な動物だった。南極海に生きる謎のタイプDをはじめ多様な生態型をもつかれらは、はたして1種なのか? 世界中の海で精力的にシャチを追い続けた記録。
目次
第1章 アメリカ、カナダの太平洋岸から
第2章 文化をもつ存在
第3章 北部北太平洋のシャチ
第4章 さまざまな生態型~南極海と北大西洋から
第5章 南半球のシャチたち
第6章 世界のシャチがたどった道、そして日本へ
第7章 シャチに未来はあるか
著者等紹介
水口博也[ミナクチヒロヤ]
1953年生まれ。京都大学理学部動物学科卒業後、出版社にて自然科学系書籍の編集に従事。1984年に独立し、世界各地で海洋生物を中心に調査・撮影を続け、多くの著書・写真集を発表。1991年『オルカ アゲイン』(風樹社)で講談社出版文化賞写真集賞受賞。2000年『マッコウの歌―しろいおおきなともだち』(小学館)で日本絵本大賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
於千代
4
シャチと言えば「海のギャング」で、海中最強クラス、そのぐらいの解像度だったが、本書を読んで大分解像度が上がった気がする。 一見同じように見えるシャチだが、実際には魚を食べるもの、海生哺乳類を食べるもの、サメを食べるものと食性が異なるグループがあり、遺伝的にも離れているようである。さらにその食性の違いから捕食圧も変わり、その海域の生物に対する影響も違うというのが興味深かった。 また本筋ではないが、そもそも「オルカ」という呼び名自体が、ローマ人たちが「海の悪魔」という意味でつけたものというのも驚きだった。2025/05/06
tksok2
3
単にシャチは海洋生物の中でも最強といったことだけでシャチ好きと言っていたが、新しい発見がたくさんあった。こういった学術的図書をあまり読むことはないが、興味ある分野において知識を深めるのはとても楽しい。最終章のシャチの未来についての解説・仮説は示唆に富む内容で一シャチファンとしては今後について憂慮すべきことであると感じた。また時間ができた時にでも読み返したい。2025/04/26
Sunekosuring
2
図書館本。大変興味深かった。シャチは好きだが詳しく知らない自分にとって新鮮な驚きの連続だった。シャチは母系社会で閉経後も賢老婆として特に息子の面倒をみるとか、主に狩る獲物によって雄弁な群れと無口な群れがあるとか、氷河期を乗り越えはしたもののそれで遺伝的多様性が失われたとか、知らないことばかりだ。だが一番衝撃なのが有害物質の蓄積が母乳を通じて子供に濃く受け継がれることで生殖障害率が高まり数が大幅に減ると予想されていることだ。すでに溜まったものは抜きようがないため手遅れであり言葉を失う。2025/02/06
がみ
1
「七つの海のティコ」を観てからずーっとシャチが好きで、海のギャングとか残虐性が高いとかマイナスな事を言われててもとにかくシャチが可愛い。シャチが表紙のものは手にとってしまう。シャチを知れば知る程、人間がシャチに対して(シャチだけでなくすべての海洋生物について)いかに悪影響を及ぼしているかが分かる。 鴨川シーワールドで初めてシャチを観たときは感動したけど、シャチの事を詳しく知ると本来居るべき場所ではないのは確か。いろいろと考えさせられる一冊。 ちなみに、タイプ別ではアイパッチが大きいタイプBが好き。2025/08/31
-

- 電子書籍
- 最良選択問題の諸相 - 秘書問題とその…
-
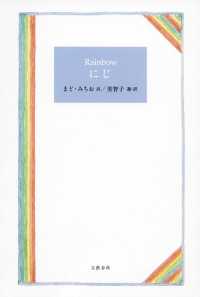
- 和書
- にじ