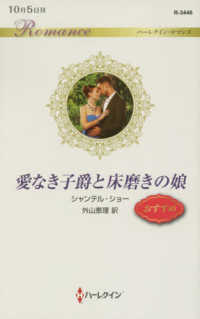内容説明
日本社会のアクチュアルな分析、人間的な価値、総合的な視野、21世紀のグローバル・スタンダードへ。解体から再生へ、その展望を探る。
目次
1 総論―村落・地域社会の変動と社会学
2 農家生活と農村社会の変動
3 村落と農村社会の変容
4 現代日本の都市‐農村関係の諸位相―都市‐農村間の地域移動をてがかりにして
5 開発と地域社会の変動
6 地方自治体「構造分析」の系譜と課題―「構造」のすき間から多様化する地域
著者等紹介
蓮見音彦[ハスミオトヒコ]
和洋女子大学学長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
たばかるB
12
仕事用。(農村)社会学からの視座。明治以降の農村の近代化過程は西洋のそれとは違い、農業・人口生産力のために「村社会」を維持する方針がとられていた。戦後の工業の発達・ならびに消費の多様化で兼業農家と出稼ぎが増加。人口が都市部に集中し人口動態が変化する。■現在の内部問題はムラを維持する(水利の整備などの共同作業)ための人間関係の相互互恵性が、農業の生産高低下による収益低下などで困難になっていることがある。その補完としての自治体での補助が必要になっているとする、■その他も基礎的な分析枠組みは網羅している教科書。2023/02/14
かぺら
2
農村社会学の概説書。戦後日本の農村が農業政策や経済成長の過程で如何に変容し(変容させられ)てきたかが論じられている。都市社会学とは異なり、理論的アプローチは確立されておらず、伝統的な民俗学とも類似した生活史的分析が多用される。農村の現状を政策、農機具の機械化、都市との関係、開発にフォーカスしながら章が進み、最後に学説史の反省が入る構成は学際的領域ならではの展開だなと感じた。ちなみに元々は全総の解説目当てで読んだ。2021/10/04