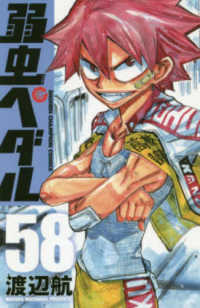出版社内容情報
戦後あたらしい地域社会の再建の希望をこめて設立された全国1万5000館の公民館.いま社会と制度の激変のただなかにあるその歴史を語りなおし,未来へとつなぐ試み.全国公民館連合会の会誌『月刊公民館』で好評連載を単行本化(2の「実践篇 」は2019年春に刊行予定).
序 社会と個人をめぐる運動
第1章 私たちはどこにいるのか
第2章 戦後の公民館構想の特色
第3章 2つの「公民館のあるべき姿と今日的指標」の観点
第4章 自治公民館と「近代化」への志向性
第5章 歴史的イメージとしての公民館――寺中構想再考
第6章 高度経済成長と社会教育の外在・内在矛盾
第7章 生涯学習の時代と「第3次あるべき姿」
第8章 社会教育終焉論と生涯学習批判
第9章 住民自治と公民館
第10章 「自治」としての〈学び〉へ
結び 当事者になる場の新しい方向
Reshaping the History of Kominkan: Discussions on the Community Learning Center in Japan
[The Making of our 〈Societies〉, 1]
Atsushi MAKINO
牧野 篤[マキノ アツシ]
著・文・その他
内容説明
いま見つめなおす公民館の可能性。激変する戦後日本の地域社会において、公民館はどうあろうとしてきたか。その稀有な我々の場所と、新しい社会・まちづくりを考える人必読の、『月刊公民館』特別連載の書籍化。
目次
社会と個人をめぐる運動
私たちはどこにいるのか
戦後の公民館構想の特色
二つの「公民館のあるべき姿と今日的指標」の観点
自治公民館と「近代化」への志向性
歴史的イメージとしての公民館―寺中構想再考
高度経済成長と社会教育の外在・内在矛盾
生涯教育の時代と「第三次あるべき姿」
社会教育終焉論と生涯学習批判
住民自治と公民館〔ほか〕
著者等紹介
牧野篤[マキノアツシ]
1960年生まれ。東京大学大学院教育学研究科教授。名古屋大学大学院教育学研究科博士課程修了。博士(教育学)。中国中央教育科学研究所客員研究員。名古屋大学大学院教育発達科学研究科助教授・教授を経て、2008年より現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
takao
Tatsuo Mizouchi
あわせみそ
-
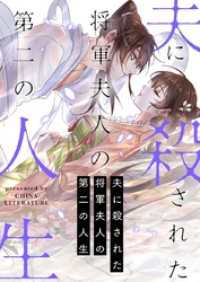
- 電子書籍
- 夫に殺された将軍夫人の第二の人生【タテ…
-
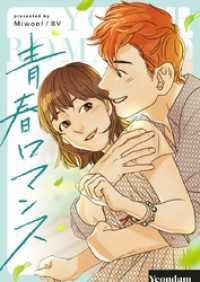
- 電子書籍
- 青春ロマンス【タテヨミ】第13話 pi…