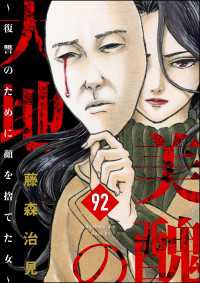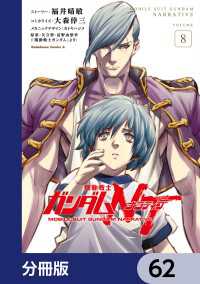出版社内容情報
「この本は、そういった毎日のくらしの中で、算数や数学がどのように活用されているかということをわかっていただくために、私の思いつくいくつかの例をあげてみたものです」(著者)。絵や音楽など暮しのあちこちにひそむ数学を知れば、世の中の見え方がちょっと変わる。おもしろく読めて論理的思考法が身につく、12のレッスン。〈解説〉森田真生
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
モリー
86
本書が音楽の中に潜む数学的規則性を数式化して見せてくれたことで、人の心を魅了する音楽の謎に迫れた気になり、一人悦に入っております。ドレミファ…の隣り合う音が等比で変化することを初めて知りました。(学校で習っていたのかも…。💦)ある音を半音上げるには、その振動数を1.059倍すればよいそうです。なを、1.059の12乗は2。それを(1+0.059)の12乗は2と書き直せば、1を元金として年利(複利)5.9%で預けた場合、12年で元金が2倍になることを示しています。私の定期預金の利率を見直しました。2021/11/28
へくとぱすかる
50
著者没後すでに30年を過ぎているが、新刊で文庫化されているということは、親しみやすく読書できる数学の本がいかに少ないかを表しているように思える。こういう分野は新しい話題だけの本を作るのが難しいのが理由だろうか。原著は1962年だが、そのわりに古さが少ないと感じられるのは、「暮しの」と称していても、あくまで数学を中心にしようという方針があったのだろう。数式を機械的に解くよりも、その原理を納得していこうという書き方が貴重だ。同じ数字がならぶ数式や、指を使ったかけ算など、じっくりと読み返したいエピソードも多い。2024/04/27
niisun
31
半世紀以上前に書かれたものですが、普遍的な内容なので違和感なく、楽しく読むことができました。学校で習う教科の中で一番苦手だった数学。とても平易に解りやすく解説されてますが、それでも数式が出てくると条件反射的に脳が思考を遮断してしまうのは変わらないですね(笑)それでも、“英語と数学”“計算されたドレミファ”“1961年のなぞ”“掛け算世界めぐり”など、知らないことがたくさんあって興味深く読めました。とくに子どもが毎日ピアノを弾いているので、ドレミが振動数の比率から決定されているというのは、なるほど!でした。2024/06/22
katsubek
30
なんと、60年近くも前の本である。ところどころに古めかしい表現が見られる。が、それがまた、楽しい。そのころの表記や表現、意識や常識を拾いながら読む。文系の人間でも楽しめる。ところもある。ふわっと読むのがよかろう。2020/07/06
tetsu
22
★3 矢野健太郎といえば40年以上も前に受験でお世話になった人です。まだ本をだしているんだと思って読んでみた。初版が2020年4月である。 中身の表現が古めかしいなぁ、などと感じながら読み終えると、1962年7月の日本放送出版協会刊のものを中公文庫として出版したものでした。 著者は故人となっていました。ご冥福をお祈りいたします。2022/03/17