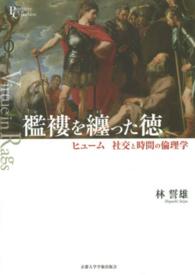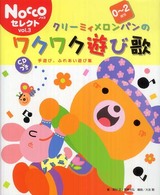出版社内容情報
人生いかに生くべきか――この永遠のテーマをめぐって、稀代の批評家は正しく問い、物の奥まで見きわめようする姿勢を貫いた。佳篇「私の人生観」を中心に「信ずることと知ること」、ベルグソン論「感想」(第一回)ほか、著者の思索の軌跡を伝える名随想集。〈解説〉水上勉
内容説明
人生いかに生くべきか―この永遠のテーマをめぐって、稀代の批評家は正しく問い、物の奥まで見きわめようとする姿勢を貫いた。名講演「私の人生観」「信ずることと知ること」を中心に、ベルグソン論「感想」(第一回)ほか、著者の思索の軌跡を伝える随想集。
目次
私の人生観
中原中也の思い出
菊池寛
ゴッホ
セザンヌ
人形
樅の木
天の橋立
お月見
季
踊り
さくら
もみじ
花見
DDT
ゴルフの名人
スポーツ
スランプ
オリンピックのテレビ
感想
信ずることと知ること
著者等紹介
小林秀雄[コバヤシヒデオ]
1902(明治35)年、東京生まれ。文芸評論家。東京帝国大学仏文科卒業。29(昭和4)年、雑誌『改造』の懸賞評論に「様々なる意匠」が二席入選し、批評活動に入る。第二次大戦中は古典に関する随想を執筆。77年、大作『本居宣長』(日本文学大賞)を刊行。その他の著書に『近代絵画』(野間文芸賞)など。67年、文化勲章受章。83(昭和58)年、死去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
イプシロン
40
批評家というものが嫌いだった。恐らく今でも得手勝手な自己の理想を拠り所として批評するような評論家は嫌いである。しかし、本作を読んでまっとうな批評家というのは、そのような評論家を指すものではないと気づけたのは大きな収穫だった。誰にとっても普遍的な真理――世界と一体になる生き方――を拠り所としているある人物やその人の作品について、そのような生き方がどのように滲みでているかを批評するのが、まっとうな評論家なのだと気づかされたからだ。本作でそうした小林の思想が最も色濃いのは「私の人生観」であり、2020/04/09
里愛乍
35
表題作は元より、全編比較的解しやすい、また思わず魅入ってしまう言葉で綴られた文章が纏められた一冊となっている。それ故に既読作品が多かったが、読み直して今、やはり自分にとってこの人の作品は何年も繰り返して読む類なのだろう。中原との文は何度読んでも切ないし大好きだし、菊池寛については敬愛している様が有り有りと伝わってくる。とりわけ一番面白かったのは『感想』だ。これは安吾が書いていた『教祖』の件か。童話と経験とは流石に巧いなと感動する。水上氏の解説が秀逸、ここに本書の全てが書かれていると思う。2020/06/17
Gokkey
12
難解な文体の根底には実存主義の哲学者のような思想的核心がある。その核心が引き寄せる素材は文学のみならず芸術、歴史など幅広い。特に印象に残ったのが、セザンヌの批評のコラムでの「画家とは言わば視覚という急所を自然の強い手で押さえられた人間なのだ。自然を見るとは自然に捉えられる事なのだ。」つまり自然に包み包まれ、主体としての自分も自然の一部として在る。この調和の中で生き、その瞬間を切り取ってきた昔からの日本人の心にある生得の直感を何よりも大事にする。それは岡潔氏との対談でも述べていた「情」そのものなのだろう。2020/10/15
shouyi.
5
若松英輔さんが人生を変えた一冊としてあげていたのでどうしても読みたくなった。表題どおり人生について小林秀雄が述べたものを集めたもの。最初の「私の人生観」という講演から已に打ちのめされる。若松さんのように手元に置いて何度も読みたい本だ。2020/03/22
さとう
3
わたしの人生観流し読み、信ずることと知ることのみ読了2020/07/05