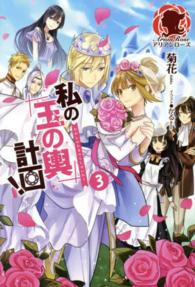出版社内容情報
よく老いることは、むずかしい。「若さという神話」への無自覚で強迫的な執着は虚しい。ならば、望ましい「年寄り」のモデルはあるのか? 歳をうまく取れないために生じる恥、勘違い、いかがわしい振る舞い。老人たちの不安に向き合ってきた精神科医が、臨床現場での知見と数多くの文学作品の読解をもとに、老いゆく人の心に迫る。哀しくもおかしな老いの見本帳。〈解説〉宮沢章夫
内容説明
老いについて語ることは、幸福について考えることに重なる―。認知症への恐れ、歳を取りそこねるために生じる恥や勘違い、若さへの見苦しい執着。一方、歳を経たがゆえの味わいとは。精神科医が、臨床現場や文学作品のなかに、身につまされる事例や望ましい「年寄り」の姿を探る。哀しくもおかしな老いの見本帳。
目次
序章 初老期と不安
第1章 孤独な人
第2章 鼻白む出来事
第3章 老いと勘違い
第4章 孤島としての老い
第5章 中年と老年の境目
第6章 老いと鬱屈
第7章 役割としての「年寄り」
第8章 老いを受け入れる
著者等紹介
春日武彦[カスガタケヒコ]
1951年、京都府生まれ。日本医科大学卒業。医学博士。産婦人科医を経て精神科医に。精神科専門医。都立中部総合精神保健福祉センター、都立松沢病院精神科部長、都立墨東病院神経科部長などを経て、現在、成仁病院院長。臨床の傍ら専門書・一般書・書評などの執筆を旺盛に続けている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
阿部義彦
17
精神科医の春日武彦さんの、老いに関するエッセイと簡単にはいえないかなあ?可也文学寄りで、文学の中に出てくる年寄りに寄せて、感想や新たな生き方を模索したり、他山の石として、こうはなりたくないなあ、等と嘆息したり。味わい深い読み物です。吉行淳之介さんと植草甚一さん等も面白かったし、可也マイナーな作家の年寄りの振る舞いや、実際に著者が見聞きした、不思議な年寄りの話なども参考になりました。60前後で突然警察沙汰になる年寄りが増えてるそうで、自分も含めてそうならないように自戒したのも含めて面白かった。2019/08/10
amanon
7
ごく最近の作品かと思えば、実際は九年前に出たものだとのこと。当時の著者と同じく五十代の渦中にある者として何かと身につまされる記述が多い。「ああ、俺もこんな風においていくのか…」と。それと共に本書にこれでもか!というくらいに登場する滑稽で、はた迷惑で、でもどこか憎めない老人のエピソードがまさに「味わい深い」。また、老いの在り方が大きく変化し、昔のような典型的な「老人」になることが難しい…というか、殆ど不可能になったという事情を改めて認識。上の世代の年の経方が殆ど参考にならない現状から一体何を学ぶべきか。2020/03/18
coldsurgeon
6
表面的にあるいは内臓を含む身体的劣化が、老いることだと思っていると、大きな勘違いを生むことになる。中年から老いを自覚していたが、どうも老人になることに不安というか危惧を抱いていたようだ。老人になるというのではなく、年寄になることを意識しなくてはいけないようだ。いろいろな文学作品(その多くが、未知であった)の引用で、老いることを考察している。意外と面白かった。2019/10/01
出口求
5
春日先生ファンであれば思わず「ニヤリ」としてしまう、「老いる」から連想される思考・小説などをまとめた一冊。ちなみに執筆当時はまだ50代だったようで、「鬱屈精神科医」シリーズで登場するお母さまの話などが出てきます。当方30代後半ですが、身につまされる文章だらけです。粋に思われよう、かっこよく老人になろうという意気込み自体がすでにあからさまで恥ずかしいとか、歳をとっても悩み事は尽きることがないとおっしゃる春日先生。やっぱりそうなのかという気持ちになりました。2019/08/05
Ryoko
4
このての本は耳障りの良い文章が並べられたものが多いけど、この本は違った。「こんな風に書いていいの?」と思うくらいはっきりと書かれている(作家さんに対する悪口多し)。その分深く頷ける箇所もたくさん。男性は定年間際、女性はもう少し早い時期に「老い」を感じて精神的に落ち込むとあってなるほどと思った。女性は見た目、男性は仕事に拘っているということか。2019/06/30
-
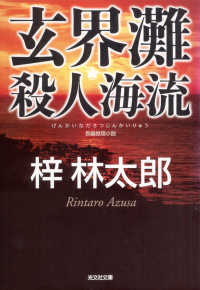
- 電子書籍
- 玄界灘殺人海流 光文社文庫


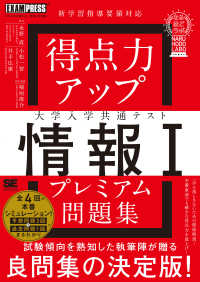
![定年・再雇用の法律実務 最新テーマ別[実践]労働法実務](../images/goods/ar2/web/imgdata2/48451/4845119285.jpg)