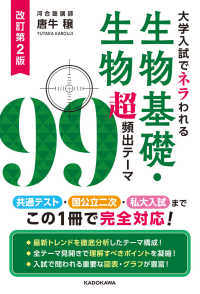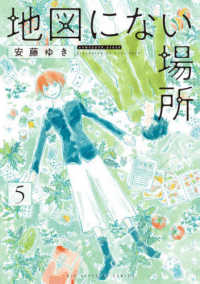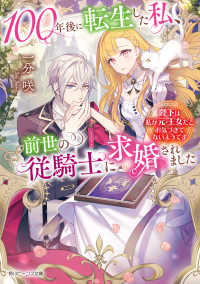内容説明
熱烈歓迎レセプションの親疎序列から批林批孔の状況を類推し、洛陽の隋唐期地下糧食庫を見て、安禄山を、楊貴妃を、さらに青銅・鉄器文化に思いを致す。歴史の中に生きる作家司馬遼太郎が文革後の中国を行く思索紀行。
目次
万暦帝の地下宮殿で
延安往還
流民の記憶
孔丘の首
洛陽の穴
琉璃廠の街角で
北京の桐の花
伝国の書物
北京の人々
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
優希
92
文化大革命後に中国を訪れた司馬さんの紀行文古き時代と現代の変わり方に想いを馳せています。その視点は興味深く、歴史作家として、歴史の中で生きてきたことを感じさせます。とはいえ、40年前の中国事情なので、また今は違っているでしょう。2017/05/06
i-miya
62
2014.02.01(01/31)(つづき)司馬遼太郎著。 01/31 (p290) 1975、中国招待旅行。 見聞の自由の有無、帰国し、なお魂魄だけが旅を続けているかのような・・・。 ◎万暦帝の地下宮殿で。 北京郊外の野に明の十三陵がある。 明、第十四代、日本の戦国から徳川初期まで在位した万暦帝(1563-1620)の墳墓。 厳文井氏。 日本作家代表団、団長、井上靖、芙美夫人、戸川幸夫、水上勉、庄野潤三、小田切進、福田宏年、他日中交流協会2名。 2014/02/01
i-miya
52
2013.12.25(12/25)(つづき)司馬遼太郎著。 12/24 (p288) 古典文明と生活文明、中国、切れ目なく連続している。 その連続を断ち切ること、その段階では容易だが、実行の段階になると、途方もなく大掛かりな仕掛けと、演出のための政治力学がいる。 見ようによっては、古代的な世界が千万の快刀乱神によってふたたび中国の隅々にわたって荒れ狂っているように見えた。 友人富士正晴、思想の如何にかかわらず、中国人と言えばすべて好きというご仁。 2013/12/25
i-miya
42
2013.11.17(2013.11.17)(再読)司馬遼太郎著。 2013.11.15 (あとがき) 幼い頃漢文を習って文王も、子路も蕭何も、虞美人も、王莽も、李白も、杜甫も、安禄山もみな自分たちが共有する過去に棲息しともに外国人とは思えなかった。 現代中国語はあきらかに外国語であるという平凡な事実に驚かざるをえない。 長安に入ってきたキリスト教ネストリウス派。 唐詩にもあるが、「大秦景教流行中国碑」 中国が連続した一つの中国文明であるに相違ないと私が目を見張ったのは、 2013/11/17
時代
13
文革後の中国をゆく司馬さん。思索紀行。新中国の変わり様に思いを馳せる。と言ってもこれは40年前の事であり、今の中国とは全く違っている様である。中国史は不勉強なのであまりピンと来なかった×2016/12/07