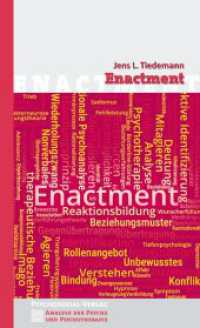内容説明
本書はフッサールが最晩年、ナチスの非合理主義の嵐が吹きすさぶなか、ひそかに書き継いだ現象学的哲学の総決算である。彼はその時代批判を、近代ヨーロッパ文化形成の歴史全体への批判として展開し、人間の理念をめぐる闘争の過程であった歴史そのもののうちに、自らの超越論的現象学の動機を求める。
目次
第1部 ヨーロッパ的人間の根本的な生活危機の表現としての学問の危機
第2部 近代における物理学的客観主義と超越論的主観主義との対立の起源の解明
第3部 超越論的問題の解明とそれに関連する心理学の機能
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かわうそ
41
科学が生活世界を解明するという使命を担いながらも生活世界を前提にしているということ、生活世界は科学の断片として扱われるのにもかかわらず、実際には普遍性を有しているということなのです。つまり、一般的には科学的な客観が主観を凌駕したと思われているのに実のところ、客観は主観を拡大したにすぎず、主観的相対的の範囲内から抜け出すことができずにいます。 また、フッサールも言っているように一般的な学問は未知から既知へ移行するのが定石ですが、哲学書を読んでいると既知が未知へと移って行く感覚に陥るのは僕だけではないでしょう2023/01/19
イプシロン
23
本著を読むなら、少なくとも「(フッサール)現象学」について概略を知っていることが前提と言える。本文では現象学用語の使用が避けられ、哲学領域では比較的一般化された用語が使われているが、現象学を知っている人からすると、かえってそのせいで理解しにくい部分があるとも言える。ともあれ、「何となく」という気持ちで読解できる著作ではないとは言える。第一部、第二部においては、現象学への道を阻害した要因をいくつか挙げている。ガリレイによって進められた極端な「理念化」。デカルト起源の「心身二元論への道」また、自我があることを2024/04/07
34
22
フッサールが生活世界と呼ぶものは、地図なしでどこにでも行ける見慣れた土地のようなもので、実践的関心に支配された「根源的な明証性の領域」である。しかし逆説的なことに、そのあらかじめ与えられている滑らかな地平は、知的関心を向けるとその明らかさが蒸発してしまうようにおもわれるのである。ちょうど見慣れたはずの土地で迷う経験に似て、それまで意識しないでどれくらいのことを遂行してきたのかが不意に意識される。それとともに、根源的な明証性のなかに身をおきたいという現象学の欲望は、不可能な欲望であることが顕にされるだろう。2018/07/12
Ex libris 毒餃子
15
訳出が上手いのかも知れないが、フッサールにしてはわかりやすい。そりゃ、名著になる。ガリレイやデカルトから出発しないと近世の哲学と科学がわからないのだが、なかなか長い。ただ、それを下地にしないと現象学の必要性がわからない。2025/09/01
春ドーナツ
15
付録二「幾何学の起源について」という小文の存在は大きかった。「セレクション」、「草稿」、本書の内容は大雑把に言えば同じである。反復することによって、少しでもフッサールの文章や考え方に親しむことができたらと、こいねがう。でもねえ、集中力が絶対的に途切れて、何度も中断を余儀なくされたし、内容が頭に入ってこなくて上滑りすることしきり。途方に暮れた私は付録二を紐解き始めた。幾何学というワンテーマで、現象学のとっつきにくい作法を敷衍した論文だったのである。あくまで上澄みの泡のひとつ程度だけれど腑に落ちる経験をした。2024/02/04
-
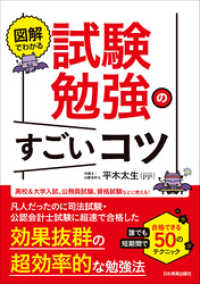
- 電子書籍
- 図解でわかる 試験勉強のすごいコツ 誰…
-
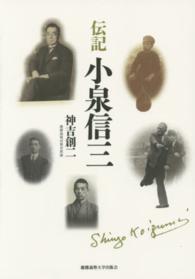
- 和書
- 伝記小泉信三