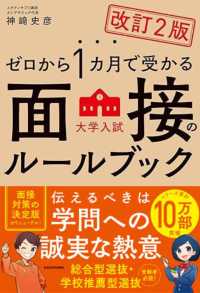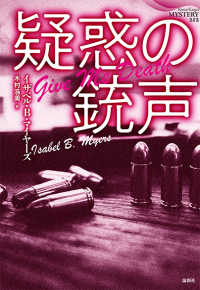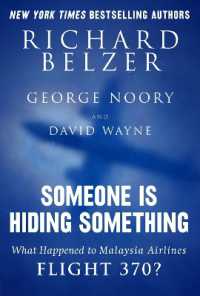内容説明
食べものには明確な一つの道がある。どのような食べものが、どんな道を辿り、どう伝わったのか。コンブの道、黒潮の道、大陸の道など、さまざまな食物伝播のルートを綿密に調査、取材し、日本各地の食文化の伝承に光をあてる。わが国の伝統的な食生活が失われゆく昨今、日本の食文化の見直しを一考させる好著。
目次
プロローグ 食べものには道がある
1 コンブのたどった道
2 黒潮にのったしょうゆと魚
3 街道を伝わる料理
4 海を渡る食べもの
5 大陸からの贈り物
6 エリアを分ける食習慣
7 人でつながる食べものの道
8 食べものが道をつくる
エピローグ 食べものの道の消失
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ナウラガー_2012
0
若狭街道=鯖の道:鯖街道:小浜から京都まで100kmあり、新鮮な鯖に塩をして三日目に京都の市場に並ぶころには塩が馴染み美味しい/和歌山県と銚子との関連性:昔は黒潮に乗って遭難したりすると房総半島へ流れ着いた。そのうち黒潮にのって漁師が房総半島までやってきて漁をするようになり、やがて定住するように../銚子の醤油、西宮との関係:1616年田中原蕃は西宮の真宜九郎右衛門のすすめで溜醤油を醸造した。これが、銚子での醤油醸造の始まり。江戸からの帰り船で赤穂の塩を運び、常陸の小麦、筑波の大豆が入手可能であったのも2012/01/24