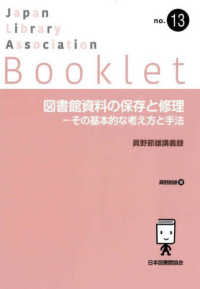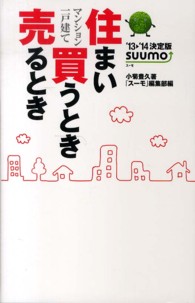内容説明
21歳で結婚し、31歳で死別された妻が、大作曲家である夫マーラーの人と芸術とその時代を、苦悩と愛惜をこめて描く。
目次
最初の出会い―1901年
1902年1月
結婚、そして新婚生活
光輝ある孤立―1903年
1906年
非しみと恐れ―1907年
秋―1907年
新世界―1907~1908年
夏―1908年
新世界―1909年
嵐―1910年
夏―1910年
第8交響曲―1910年9月12日
クリスマス―1910年
終焉―1911年
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ふじさん
83
クラシックTVでマーラーの特集を見て、この本を数十年ぶりで読み返した。21歳で結婚し、31歳で死別された妻・アルマ・マーラーが、大作曲家であるマーラーの人と芸術を生きた時代を、苦悩と哀惜をこめて描いた回想の書。グスタフ・マーラーの人柄、生活ぶり、音楽その他についての考え方、それから彼をとりまく環境、友人、同時代の音楽生活の有り様などを書いたものとしては、たしかにこれは大事な資料だし、書き手の性格を反映して、読み物としてもとても面白かった。アルマの思いが強い分、果たしてどうだろうかと思える内容も多々あるが。2025/08/30
松本直哉
30
このごろ演奏の機会の増えたアルマ作曲の歌曲を聴くにつけても、結婚のときに作曲の筆を折るように夫から命じられたのは痛恨で、もっと書いて欲しかったと思うし、女性ゆえにキャリアを断念したことへの悔いと夫の無理解への恨みが行間ににじむ。夫の作曲の現場に居合わせ、その最初の聴き手となった彼女の最も評価するのは第六交響曲。「彼のどの作品も、この曲ほど心の深部から直接に出たものはない」という評価は彼女の高い審美眼を示す。その第一楽章の第二テーマの空を飛ぶような旋律はグスタフがアルマを表現しようとしたものだった。2024/03/09
Wataru Hoshii
10
マーラーファン必読の書で、実家の本棚に昔からあったのだがなぜか手に取らず、ようやく読了。亡父の付箋と書込みがたくさん。有名なマーラーの逸話の数々はほぼこちらがソース。よく指摘されるように誤りや書かなかったことも多く、彼女の主観による「物語」の側面も強い伝記だが、それを考慮しても貴重な内容。戦前ヨーロッパの文化的雰囲気はツヴァイクとも響き合うし、マーラーの人となりもよくわかる。ブラームスやシェーンベルクとの交流についての記述も貴重。ニューヨークがヨーロッパを超えるクラシックの現場になっていたこともわかる。2024/08/15
またの名
9
「お前のよりロットさんの曲の方がいい出来に決まってるじゃないか」とマーラー母をして息子に向かって言わしめた学友ロットが発病し精神病院で作曲する人になり、成長して音楽監督に就いた頃に友人ヴォルフはマーラー家の戸を叩き「自分はマーラーだが」などと話して病院行き。シェーンベルクやシュトラウスといった濃い交友関係に加えディープな時空間で展開された音楽家の生涯には妻の浮気みたいな事件も起きたがその辺はふわっと濁しつつ、妻が焦りを持って証言するのは、ユダヤ人マーラーの生前の偉業を次々抹消する第三帝国の動きを前にして。2019/10/21
松本直哉
4
アルマはR.シュトラウスのことを度し難い俗物をして描いているが、その彼にあのような天上的に美しい曲がどうして書けたのだろう。私は特に彼の晩年の「変容」「オーボエ協奏曲」「4つの最後の歌」などを思い浮かべているのだが。その反面マーラーの音楽は人間性と音楽がぴったり一致していて、彼の苦悩や喜びがそのまま音楽に反映している。この回想録から浮かび上がるマーラーの姿は、彼の音楽そのもののように思える。それにしても、20世紀最初の10年、第一次大戦前夜の文化の豊かさと多様性に驚く。戦争がそれを粉々に打ち砕いた。