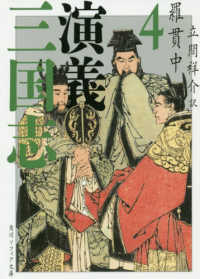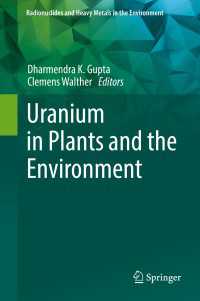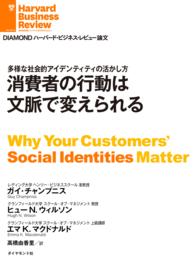出版社内容情報
日本文学は「どうしても翻訳できない言葉」で書かれてきた、と大江健三郎は言う。事実、谷崎も川端も三島も、英訳時に改変され、省略され、時に誤読もされてきた。なぜそのまま翻訳することができないのか。どのような経緯で改変され、その結果、刊行された作品はどう受け止められたのか。一九五〇~七〇年代の作家、翻訳者、編集者の異文化間の葛藤の根源を、米クノップフ社のアーカイヴ資料等をつぶさに検証し、初めて明らかにする。
目次より
序章 日本文学翻訳プログラムの始まり――ハロルド・シュトラウスとクノップフ社
第一章 日本文学の異質性とは何か――大佛次郎『帰郷』
第二章 それは「誰が」話したのか――谷崎潤一郎『蓼喰う虫』
第三章 結末はなぜ書き換えられたのか――大岡昇平『野火』
第四章 入り乱れる時間軸――谷崎潤一郎『細雪』
第五章 比喩という落とし穴――三島由紀夫『金閣寺』
第六章 三つのメタモルフォーゼ――『細雪』、「千羽鶴」、川端康成
第七章 囲碁という神秘――川端康成『名人』
終章 日本文学は世界文学に何をもたらしたのか――『細雪』の最後の二行
内容説明
日本文学は「どうしても翻訳できない言葉」で書かれてきた、と大江健三郎は言う。事実、谷崎も川端も三島も、英訳時に改変され、省略され、時に誤読もされてきた。なぜそのまま翻訳することができないのか。どのような経緯で改変され、その結果、刊行された作品はどう受け止められたのか。米クノップフ社のアーカイヴズ資料等をつぶさに検証し、一九五〇~七〇年代の作家、翻訳者、編集者の異文化間の葛藤の根源を初めて明らかにする。
目次
序章 日本文学翻訳プログラムの始まり―ハロルド・シュトラウスとクノップフ社
第1章 日本文学の異質性とは何か―大佛次郎『帰郷』
第2章 それは「誰が」話したのか―谷崎潤一郎『蓼喰ふ虫』
第3章 結末はなぜ書き換えられたのか―大岡昇平『野火』
第4章 入り乱れる時間軸―谷崎潤一郎『細雪』
第5章 比喩という落とし穴―三島由紀夫『金閣寺』
第6章 三つのメタモルフォーゼ―『細雪』、「千羽鶴」、川端康成
第7章 囲碁という神秘―川端康成『名人』
終章 日本文学は世界文学に何をもたらしたのか―『細雪』の最後の二行
著者等紹介
片岡真伊[カタオカマイ]
国際日本文化研究センター准教授、総合研究大学院大学准教授(併任)。1987年栃木県生まれ。ロンドン大学ロイヤルホロウェイ(英文学)卒業、ロンドン大学ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン修士課程(比較文学)修了。総合研究大学院大学(国際日本研究)博士後期課程修了。博士(学術)。ロンドン大学東洋アフリカ研究学院シニア・ティーチング・フェロー、東京大学東アジア藝文書院(EAA)特任研究員を経て、2023年より現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
踊る猫
Dolphin and Lemon
Mits
takao