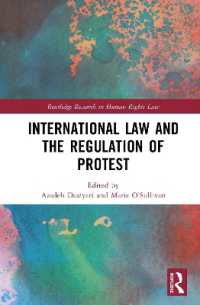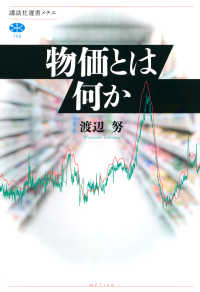出版社内容情報
かつて中米に栄えた古代マヤ。密林に眠る大神殿、高度に発達した天文学や暦など、神秘的なイメージが強かったが、最新の考古学研究で「謎」の多くは明かされている。解読が進んだマヤ文字は王たちの事績を語り、出土した人骨は人びとの移動や食生活、戦争の実態まで浮き彫りにする。長年発掘調査に携わった著者が、マヤ文明の実像を描き出す。
内容説明
碑文が紡ぎ出す王たちの物語、レーザーが発見した道路網・水道網・遺構の数々、人骨が伝える古代人の個人史…王朝の興亡から戦争や移民の実態まで、最新の考古学が解き明かす古代文明の謎。
目次
序章 マヤ文明研究の歴史
第1章 考古学と形質人類学―バイオアーキオロジーの誕生
第2章 南部周縁地―グアテマラ南海岸地方、エル・サルバドル、ホンジュラス
第3章 人は動く―移民動態の研究
第4章 グアテマラ高地、マヤ王国の終焉
第5章 古代の食卓―マヤご飯
第6章 ペテン地方―密林に眠る神聖王の群雄活劇
第7章 古代マヤにおける戦争
第8章 灼熱のユカタン半島を行く
第9章 肉体は文化を語る
著者等紹介
鈴木真太郎[スズキシンタロウ]
1979年生まれ。2002年上智大学外国語学部卒業。2008年ユカタン自治大学骨人類学修士課程修了。ホンジュラス共和国コパン遺跡の調査発掘・保存業務に従事。2009年ユカタン自治大学人類学部助手。2015年メキシコ国立自治大学哲文学部メソアメリカ地域研究科博士課程修了。現在、岡山大学大学院社会文化科学研究科講師。文部科学省卓越研究員事業平成30年度卓越研究員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
六点
ころこ
翔亀
翠埜もぐら
サケ太