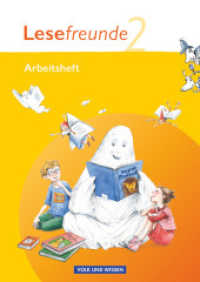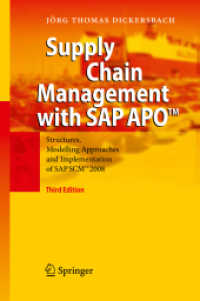内容説明
1894年の夏、日清両国が朝鮮の「支配」をめぐり開戦に至った日清戦争。朝鮮から満州を舞台に戦われた近代日本初の国家間戦争である。清の講和受諾によっていったん終わりをみるが、割譲された台湾では、なお泥沼の戦闘が続いた。本書は、開戦の経緯など通説に変更を迫りながら、平壌や旅順の戦いなど、各戦闘を詳述。兵士とほぼ同数の軍夫を動員、虐殺が散見され、前近代戦の様相を見せたこの戦争の全貌を描く。
目次
第1章 戦争前夜の東アジア
第2章 朝鮮への出兵から日清開戦へ
第3章 朝鮮半島の占領
第4章 中国領土内への侵攻
第5章 戦争体験と「国民」の形成
第6章 下関講和条約と台湾侵攻
終章 日清戦争とは何だったのか
著者等紹介
大谷正[オオタニタダシ]
1950(昭和25)年、鳥取県生まれ。大阪大学文学部卒。大阪大学大学院文学研究科博士課程退学、博士(文学)。1982年専修大学法学部講師、助教授、教授を経て、2010年より専修大学文学部歴史学科教授。専攻・日本近代史・メディア史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
とくけんちょ
51
名前は知っていたが、よくよく理解していなかった戦争。いつどのように始まって、どのように決着がついたのか。勝った勝ったとは知ってたが。近代日本にどのような影響を与えたのか、規模やその背景についても整理することができた。次は目に見える兵器や服装などのビジュアルで当時を振り返ってみたい。2023/08/04
Toska
30
日清戦争は、日露の前座などではない。それは全く異なる条件と国際関係の下、異なる目的をもって始められたものだった。戦場での進退は勿論、日清朝それぞれの政治状況や列強の思惑、日本外交の得失、国内に残された影響など、多様な視点からこの戦争を見つめ直した労作。新書のサイズでは限界に近い充実した内容と思う。戦争の道義的な部分については議論のあるところだが、実務面でも意外と失敗が多かったのに、等しく「成功体験」と回顧されてしまったのが一番の問題だったのでは。2025/08/04
Tomoichi
27
日露戦争に比べると関係図書も少なく影の薄い日清戦争を通史・メディア・社会・地域との関連など多方面から読み解く。旅順虐殺事件についても取り上げているがきっかけとなった清国兵による戦死遺体損壊や民間人に扮する行為など記す。人数についても冷静に分析している。陸奥宗光批判や日本政府や軍のドタバタ、日露戦争の遠因、朝鮮との関係など教えられることの多かった一冊でした。2018/10/03
クラムボン
22
日清戦争について一般向けに書かれた本ですが、時として、日本近代史の専門家としての「厳密さや正確さ」にこだわるためか、読み辛いところも多かった。ただこの本を読めば、当時の日本、清、朝鮮の置かれた状況や問題などが良く分かる。先ず開戦10年ほど前の朝鮮の説明から始まる。そして戦争に至るまでの日本国内の政治の動きや開戦発端の朝鮮王宮の武力占拠、豊島沖海戦、朝鮮漢城近郊から平壌への戦い、鴨緑江を越えて遼東半島での戦い、黄海開戦などが詳しく記される。そして新聞社の対応や国民の関心度など社会面についての記述も詳しい。2025/04/03
coolflat
22
日清戦争は、①朝鮮との戦争(日朝戦争)、②清との戦争(日清戦争)、そして下関条約後の台湾領有における、台湾の漢族系住民(台湾民主国)との戦争(台湾征服戦争)という、3つの戦争相手国・戦争相手地域の異なった戦争の複合戦争である。一般的には、狭義の②を指すが、本書を読むと、この②の日清戦争は、実態的には日本軍vs清軍の戦争というよりは、日本軍vs李鴻章の私的軍隊の戦争であることがわかる。実は清軍敗退の原因はここにある。政治的にも、軍部的にも統一的仕組みがなかった。李鴻章の孤軍奮闘に頼るようでは勝ち目がない。2020/08/01
-
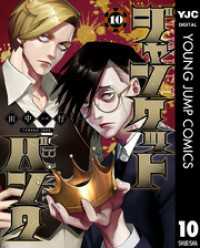
- 電子書籍
- ジャンケットバンク 10 ヤングジャン…