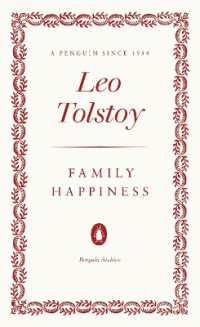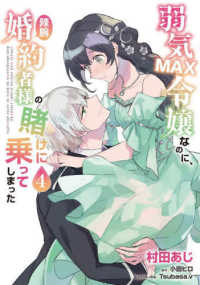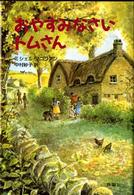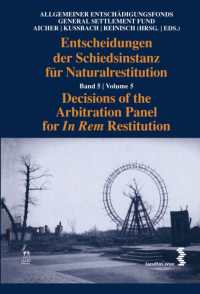内容説明
「均衡」「協調」「共同体」―近代ヨーロッパが生んだ国際秩序の基本原理である。本書はこの三つの体系を手がかりに、スペイン王位継承戦争から、ウィーン体制、ビスマルク体制、二度の世界大戦、東西冷戦、そして現代に至る三〇〇年の国際政治の変遷を読み解く。平和で安定した時代はいかに築かれ、悲惨な戦争はなぜ起こってしまったのか。複雑な世界情勢の核心をつかみ、日本外交の進むべき道を考えるための必読書。
目次
序章 国際秩序を考える
第1章 均衡・協調・共同体―三つの秩序原理(均衡の体系;協調の体系;共同体の体系)
第2章 近代ヨーロッパの国際秩序(勢力均衡の成立―一八世紀の国際秩序;均衡による協調―ウィーン体制;協調なき均衡―ビスマルク体制)
第3章 世界戦争の時代(国際秩序のグローバル化;秩序の挫折―二度の世界大戦;リベラルな秩序の成立―大西洋の時代)
第4章 未来への展望―グローバル化時代の国際秩序(恐怖から希望へ―冷戦期の国際秩序;「新世界秩序」の夢と挫折;「太平洋の世紀」へ)
著者等紹介
細谷雄一[ホソヤユウイチ]
1971年、千葉県生まれ。立教大学法学部卒業。英国バーミンガム大学大学院国際関係学修士号取得(MIS)。慶應義塾大学大学院法学研究科政治学専攻博士課程修了。博士(法学)。北海道大学専任講師などを経て、慶應義塾大学法学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
おせきはん
27
スペイン王位継承戦争以降の国際政治の歴史を通じて、国際秩序を形作る要素について論じています。力の均衡がベースで、それに価値の共有が加わり協調が進むと安定性は増すものの、その後、新しい勢力が台頭して力の均衡に戻るサイクルを繰り返してきたように感じました。力の均衡に戻りつつあるように見える現在、歴史から学ぶことも大切だと思いました。2025/12/28
しゃん
27
本書は、スペイン王位継承戦争から3世紀(2012年まで)に亘る国際秩序の歴史を基に、国際秩序が形成される基本原理を分析する。「均衡の体系」「協調の体系」「共同体の体系」という3つの秩序原理を基に、国際秩序がいかにして形成されてきたのかが分かりやすく解説されていた。「共同体の体系」がうまく機能するためには「価値」の共有が必要であるという点は面白かった。ここに欧州とアジアとの相違がある。本書刊行後の国際情勢の激動を考えるにあたって、本書が提示した分析の視点は有用であると思った。やはり歴史を学ぶことが大切。2020/08/10
Francis
17
冒頭に理想主義的とされる坂本義和氏とリアリスト派高坂正暁氏の論争の行方を追う文章が印象的。著者は「勢力均衡」による国際秩序の形成に重きを置きつつ、価値観の共有など協調の体系も必要であることを力説する。近代ヨーロッパ史を踏まえた著者の国際秩序の考察はとても優れたものとなっている。2017/11/13
1.3manen
14
著者は評者と同年齢。本書でTPPの自由貿易をどう切るかが興味深い。ヴァッテルの多元主義が関心を引いた(47頁~)。18Cの人のようだ。著者の説明は新書ながらもテキストとしての公平性というか、バランス感覚に優れている。特定の論者に肩入れしがちな専門家の陥屏を見事に回避している。小国の主権を守ることで勢力均衡を維持でき、国際秩序の安定をもたらすというのは重要な考えであろう。特に北朝鮮の暴走を防ぐためにも。ヒュームの貿易論にも触れられ、TPPへの視点も得られる。あとがきの同僚や上司のアドヴァイスも有効のようだ。2013/03/27
kiho
12
歴史が語る世界各国の勢力図をわかりやすく説明…今まで点として存在していた様々な出来事が、各国の思惑を背景に並べると立体的に浮き上がって来るような…日本が国力を増長していった流れもドイツのビスマルクの言葉でより明白に⭐これからの世界の構図はどうなっていくのか…。2015/12/26