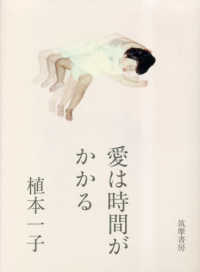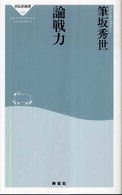内容説明
古語とは何か。「明治維新以前の言葉」ではない。江戸時代には『源氏物語』の言葉が、平安時代には『万葉集』の言葉が古語であったように、今後も書き換えが続いていくのである。江戸中期、初めて「古典をその時代の言葉で読む」方法が確立する。賀茂真淵、本居宣長らによって夥しい古語が読まれ、解釈され、『万葉集』や『古事記』は庶民に近くなる。その過程で生まれた仮説や誤りの謎を解き、言葉の本質を考える。
目次
第1章 創作される人麻呂歌―「ひむがし」が歌語になるまで
第2章 「秘す可し」を乗り越えて―近代化する古典学
第3章 幻の万葉語たち―江戸時代に生まれた古代語
第4章 濁点もばかにならない―架空の古語の成立
第5章 銭湯の古典談義―大衆化する古学
第6章 発見の時代―古学の充実
第7章 鈴虫はちんちろりんと鳴いたか―古学の呪縛
第8章 古典解釈の江戸と京都―反古学派の古典享受
終章 作者自筆本という幻想―古学の限界
著者等紹介
白石良夫[シライシヨシオ]
1948(昭和23)年、愛媛県生まれ。九州大学文学部卒業、同大学院修士課程修了。北九州大学講師を経て83年、文部省入省、教科書調査官(国語担当)となる。2009年3月、文部科学省を定年退官し、現在、佐賀大学文化教育学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
へくとぱすかる
39
柿本人麻呂の「ひむかしの~」の歌は、正しい読み方に議論が絶えないのでも有名。実は「かぎろひ」も「かたぶきぬ」も怪しいと思うのだが、ここでは「ひむかしの」に絞って紹介。結局何が正しいのか、結論はまだないようだ。何としても知りたいところではあるが人麻呂に直接訊くしかない(そんなの不可能だ)。現代はオリジナルのテクストを追求することが研究の目的だが、古典の同時代にはそんな思考はまるでなく、実用目的で活用することが当たり前だった。さて「神代文字」がこの本に登場するとは思わなかった。意外なところでお目にかかった。2025/08/23
tama
9
図書館本 はて どうして借りる気になったんだっけ?でもまあ、面白かったからいいか。「ひむがしの野にかぎろひの立つ見えて」がなんか和歌としてどうよ、というところから、漢字で音を表記していた元歌を江戸時代に「新解釈」したのがこれであり、平安時代は「あずま野の煙の立てる処見て」だったと。漢字で書いた歌にカナでルビがふってある。へえぇ、です。新解釈はいいけど、やった人の地位とかが絡むと後の時代に「おかしいものが無批判に伝わる」というお話でもありました。2017/04/13
遠野
8
架空の古語『おごめく』、松虫鈴虫論が面白かった。言葉って本当に不確実で曖昧なもの。少し時代が遡るだけで、もう再現が難しくなる。現行の言葉にしても、一つの語に誰もが共通の認識を持っているとは限らない。そんなあやふやなものを使って、私たちは交流している。言葉は生活に密着したものなのだから、理屈っぽく考えすぎるのは詮無いこと。もっといい加減で良いのだ。生きた言葉に「乱れている」と顔をしかめるのではなく、「面白い」と思える人でありたいと思った(ただし、自分が使う言葉についてはそれなりの信念を持っていたい)。2011/02/23
しんこい
7
辞典や教科書にのっている事は正しい事みたいに受け取ってしまいがちですが、読み方ひとつとっても色々な解釈を沢山の人が追求してきたのだという事がよく分かります。「そんな歌詠んだっけ(人麻呂)」というコピーで手に取りました。2011/01/21
マープル
6
おもしろい。まず本文の前に帯の「そんな歌、詠んだっけ?―――柿本人麻呂(談)」というのが秀逸。担当者に座布団一枚。そして、内容では、こういうのを学校で少しでもエピソードとして話してくれれば、もっと古文に興味を持てただろうになぁという話題が多数。いわゆる(科学的な)文献学っててっきり西洋だけのものかと勘違いしていた。2011/05/23