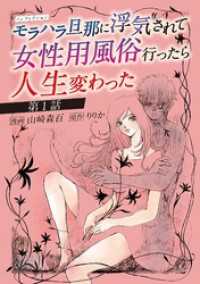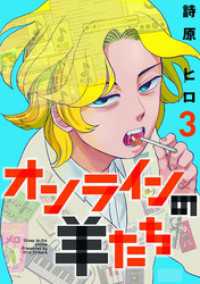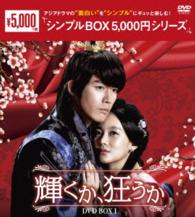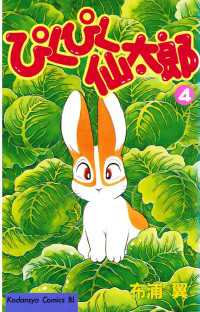内容説明
忠臣蔵の四十七士が討ち入り前に集合したのはうどん屋だったのか、蕎麦屋だったのか?日本における蕎麦の歴史は古く、縄文時代にさかのぼるが、現在の私たちが知る蕎麦(蕎麦切り)が広く食されるようになったのは江戸時代初期。うどんに替わって江戸の町に定着したのは十八世紀中頃、明和・安永以後である。蕎麦が江戸の人々にとって欠かすことのできない食べ物になっていく様子を、川柳、歌舞伎、落語などから愉しくさぐる。
目次
第1章 赤穂浪士、蕎麦屋に集合
第2章 蕎麦をめぐる光景
第3章 芭蕉と蕎麦
第4章 漢詩人、蕎麦を詠む
第5章 蕎麦の笑話
第6章 『化物大江山』のうどん童子退治
第7章 蕎麦屋仁八というキャラクター
第8章 落語で啜られる蕎麦
第9章 浮世絵の中で蕎麦は
著者等紹介
鈴木健一[スズキケンイチ]
1960(昭和35)年、東京都生まれ。東京大学文学部卒業。同大学院人文科学研究科博士課程単位取得退学。東京大学助手、茨城大学助教授、日本女子大学教授を経て、学習院大学文学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
nchiba
3
江戸の本物の江戸っ子はホントに蕎麦が好きだったんだねえ。黄表紙、歌舞伎、浮世絵に落語。いろんなところで蕎麦が語られている。蕎麦で日本酒を一杯やりたくなったな。2010/11/01
takao
2
ふむ2023/01/24
糸くず
1
〈「雅」と「俗」の融合〉という観点からの蕎麦と文学との関わりに、「なるほど」という思い。新井白石の漢詩「蕎麦麺」の中国の故事まで引用した大げさな言い回しと描かれている対象とのギャップが面白い。『化物大江山』や源平合戦を題材にした笑い話を見ると、「日本人の二次創作への欲望って江戸時代から凄かったのかな」とテキトーな想像が頭に浮かんだ。2016/03/30
unknown
1
恋川春町の黄表紙本「うどんそば 化物大江山」について触れている第六章「『化物大江山』のうどん童子退治」の項がとても面白い。登場人物が全てうどんそば薬味と化す、大江山四天王パロディ本。いいユーモアだなあ。2011/10/16
食いしん坊
0
蕎麦に関する俳句、御伽草子、落語、浮世絵などから、江戸庶民に蕎麦が親しまれていく様子を案内している本。そばきりも最初はもりそばのみ、それがようやく寛政(1789-1801年)にかけそばが登場するなど、興味深い話が満載で面白い。2014/01/18