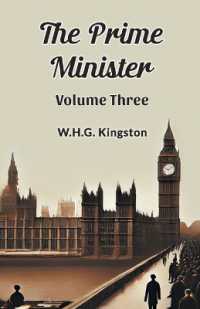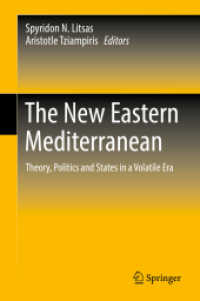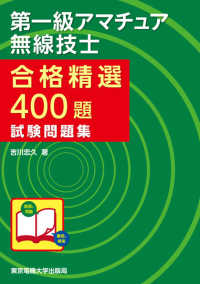出版社内容情報
一九六九年一月、東大全共闘と機動隊によって繰り広げられた壮絶な攻防戦は、なぜ戦われねばならなかったのか。内部者たちの証言。
内容説明
一九六九年一月、全共闘と機動隊との間で東大安田講堂の攻防戦が繰り広げられた。その記憶はいまもなお鮮烈である。青年たちはなぜ戦ったのだろうか。必至の敗北とのその後の人生の不利益を覚悟して、なぜ彼らは最後まで安田講堂に留まったのか。何を求め、伝え、残そうとしたのか。本書は「本郷学生隊長」として安田講堂に立てこもった当事者によって、三七年を経て、はじめて語られる証言である。
目次
その1 発端
その2 未来の大学へ
その3 バリケードのなかで
その4 ひとつの歴史の頂点
その5 日大・東大全共闘合流
その6 前夜
その7 安田講堂前哨戦
その8 安田講堂攻防
その9 安田講堂始末
その10 一九六九年、そして今
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Tomoichi
21
安田講堂が落城して40年近く経って当事者(暴れていた側)が書いた実録だが、未だ自分達のことを正当化しているから興醒める。確かに医学部のインターン問題や未だにお金にルーズな日大問題など学生が反発するのは理解できるが、目的が正しくても手段を間違えると破滅する典型例である。ご本人は東大で秀才でいらっしゃるのでその後サル学で大成されたようだが、日大の面々はどうなったのでしょう。サルの気持ちは理解できるが、人間社会が理解できないおじさんの武勇伝。しかしホーチミンをホおじさんと崇めるのには驚いた。2021/11/13
佐島楓
15
世代間ギャップといってしまえばそれまでだが、私の両親の世代と私にここまでの隔たりがあるのかと衝撃を受けた。自分が信ずる何かのために命を賭して戦う(良し悪しは別にして)ということは私以下の世代には無理な気がする。おそらくうねりを生み出せるほどのパワーもなく、リスクを回避するほうを選ぶだろう。そう思うと、ここに書かれていることが両親の青春と本当につながっているのかと疑問を覚えるほどだ。完全な理解はおそらくできない。それが悲しい。2012/10/29
モリータ
10
◆'05年刊。著者は'46年生、在野(≠大学系機関所属)の動物学者・類人猿学者。東大紛争当時は理学部人類学教室所属, 同学部のストライキ実行委員長。「本郷学生隊長」として陥落まで安田講堂で抵抗。(以降は本書未記載・詳細不明だが)逮捕され懲役2年、京大で理学博士号取得。◆当時の社会・政治の情勢や学生運動の過程や成果を客観的に振り返るための歴史的叙述ではなく、当時の青年の怒りそのままに、反国家権力・反米・反代々木の立場で、大学紛争で青年たちが抵抗し、問うたもの―特に日本の教育のダメさ―を書き綴っている。2021/08/05
ステビア
7
ドキュメントとしては一級品だが、全編を覆う感傷があまりにも甘い。死に場所を探しているんだね。2014/01/09
富士さん
5
再読。仁義なき戦いでした。佐々さんの本と比べて読むと認識のあまりの違いにクラクラします。互いに自分の都合の良い話しか書いていないというのはさておいても、この時代が、「人として問題ない」かから、「法的に問題ない」かへ、日本の価値観が移行するきっかけの時代だったのではないかと思えてきます。日本人なら当然国のために死ぬものだとか、日本人を殺したアメリカには従わないという主張を聞いていると、左翼と右翼の関係は一筋縄ではいかないことがよくわかります。まだこういう"if"もあった時代なんだと、思わずにはおれません。2020/05/22
-
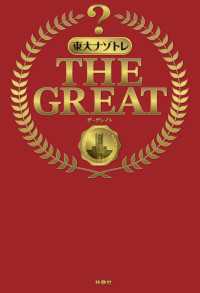
- 電子書籍
- 東大ナゾトレ THE GREAT フジ…