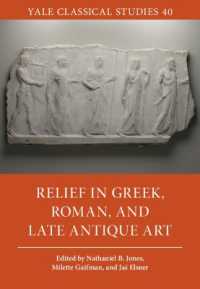出版社内容情報
18世紀後半から20世紀前半までの、私たちが最も親しんでいる「クラシック音楽」と、その前後の音楽状況の重要ポイントを詳述。
内容説明
一八世紀後半から二〇世紀前半にいたる西洋音楽史は、芸術音楽と娯楽音楽の分裂のプロセスであった。この時期の音楽が一般に「クラシック音楽」と呼ばれている。本書は、「クラシック音楽」の歴史と、その前史である中世、ルネサンス、バロックで何が用意されたのか、そして、「クラシック後」には何がどう変質したのかを大胆に位置づける試みである。音楽史という大河を一望のもとに眺めわたす。
目次
第1章 謎めいた中世音楽
第2章 ルネサンスと「音楽」の始まり
第3章 バロック―既視感と違和感
第4章 ウィーン古典派と啓蒙のユートピア
第5章 ロマン派音楽の偉大さと矛盾
第6章 爛熟と崩壊―世紀転換期から第一次世界大戦へ
第7章 二〇世紀に何が起きたのか
1 ~ 1件/全1件
- 評価
-





再読本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
naoっぴ
72
音楽を世界史の流れで紐解いていく一冊。タイトルはお堅いけど、読みはじめると著者の思いが感じられる文章で思いのほか読みやすかった。はじめ宗教のためのものであった音楽が王侯貴族の手に渡り、次第に大衆へとバトンタッチ。それに伴い曲がどんどん変わっていく様子は知的好奇心をそそられる。第一次世界大戦の直前に美しい調性を破壊するような曲や楽器が出たことは、当時の人々に精神的な乱れがあったのだろうか。漫然と聴いていたクラシック音楽、西洋世界の時代背景を知れば違う響きが聴こえてくるかもしれない。2019/02/09
キムチ
65
再読、面白すぎて内容が脳内にじんわり染む。グレゴリオ聖歌~中世のイメージではミサ そして信者の祈りの背後に流れるそれがクラシック音楽の源。その後 特に18~20C 一般聴衆に向けるポピュラーな流れに変容してきた<あたかも絵画がそうであったように>もっとも独ロマン派においては厳然たる宗教色があったし、3大Bの一人 バッハの功績は事の是非を問わず そこに大きく貢献。子供の頃 ラジオから流れるミサ曲で慣れ親しんだ音譜~モーツァルト、ベートーベン、バッハを中心に 常に耳元に有った音楽への造詣を更に掘り下げてくれる2022/10/13
zirou1984
37
こんなにも面白い新書にはそうそう出会えるものじゃない。西洋音楽の歴史、つまり中世の讃美歌から現代のポピュラー音楽までをひとつなぎの系譜と見ることで、門外漢には遠いクラシックの世界がこんなにも馴染みやすくなる。その中で17世紀から20世紀前半の流行音楽であるクラシックについて地域や時代毎の特色について触れることで、音楽を語ることが同時に芸術や時代文化を語ることへと繋がっていく。本書はクラシックの入門書であると同時に、音楽について語ることはこんなにも面白いのだと久々に思い出させてくれた良書。2017/03/31
ひと
30
教会音楽やグレゴリオ聖歌からルネサンス、バロック、古典派、ロマン派音楽を経て戦後の音楽へと到る西洋「クラシック」音楽の大きな流れを一般向けに解説してくれている本です。バロックといえばバッハとの印象でしたが、煌びやかなバロックの中でプロテスタント文化を背景としたバッハ音楽の特殊性や、教会やパトロンからプロ音楽家となって自由を手に入れた初の音楽家であるベートーベンの話、音楽の大衆化の中で普及していったサロン音楽やピアノ音楽の話などを通して、いわゆるクラシック音楽が少し身近になってきた気がします。2018/01/21
金城 雅大(きんじょう まさひろ)
29
「耳馴染みのある」と言われても全然ピンとこないほどこれまで全く触れてこなかった西洋音楽。そのような未知の世界に足を踏み入れるのは、何歳になってもワクワクする。 本書に出てくる音楽をYouTubeで探して聴きながら読むと、門外漢でもわかりやすかった。 本書が出版された2005年当時、まだいつでもどこでも聴きたい音楽を聴ける環境は整っていなかった。本書の想定読者は「ある程度クラシックを嗜んでいる人」だと著者自身も明言している。 テクノロジーの進化に伴い、昔の書物がその想定読者を拡大する好例だと思う。2019/09/15
-

- 電子書籍
- 雨の日に拾ったのは野良猫系女剣士!?【…
-

- 電子書籍
- 東京トイボクシーズ 分冊版第28巻 バ…