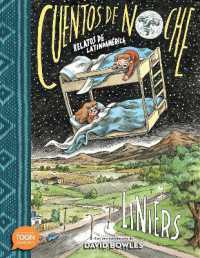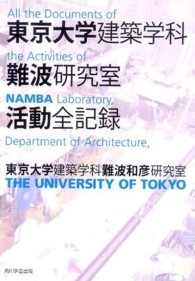内容説明
一九七〇年前後まで、教養主義はキャンパスの規範文化であった。それは、そのまま社会人になったあとまで、常識としてゆきわたっていた。人格形成や社会改良のための読書による教養主義は、なぜ学生たちを魅了したのだろうか。本書は、大正時代の旧制高校を発祥地として、その後の半世紀間、日本の大学に君臨した教養主義と教養主義者の輝ける実態と、その後の没落過程に光を当てる試みである。
目次
序章 教養主義が輝いたとき
1章 エリート学生文化のうねり
2章 五〇年代キャンパス文化と石原慎太郎
3章 帝大文学士とノルマリアン
4章 岩波書店という文化装置
5章 文化戦略と覇権
終章 アンティ・クライマックス
1 ~ 5件/全5件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mitei
147
そもそも教養とは何ぞやということから始まってて分かりやすく、如何に教養が没落して行ったのかを如実に記していたのでよかった。2010/12/03
trazom
134
人格形成・修養主義と結びついてエリートの間で受け継がれてきた教養主義が没落を始めたのは、高等教育進学率が上昇した70年代だという。エリートではなく所詮サラリーマン予備軍なのに、教養など無用だとする大学生たちの諦念。一方、社会の側も、教養知ではなく専門知(機能的な知識人)を求める時代背景。結果的に大学がレジャーランド化し教養主義が没落したんだと。でも、教養って、そんな実利志向のものなのか。読書や芸術を通じて古今の知性に触れることは、有用かどうかではなく、それ自体として人生を豊かにしてくれるのだと信じたい。2025/10/12
道楽モン
75
我が国の教養主義は、明治維新から始まった一種の立身出世(あるいは下剋上的なルサンチマン)を指している。ピエール・ブルデューの『ディスタンクシオン』を援用してフランス、イギリス、ドイツの階級社会との差異を明確に示した後、夏目漱石の『三四郎』、絶対的な教養人である丸山真男に対して大衆インテリの立場から吉本隆明が行った批判、石原慎太郎の東京大学生への怨嗟、岩波書店の歴史やカウンターカルチャーとしてのビートたけしなどを通じて、教養主義の栄枯盛衰を描く。かなり刺激的な一冊で、欧州とは異なり教養主義も底が浅いぞ日本。2023/06/30
たま
71
米津玄師(1)が最近言及して突然売れ行きが伸び、増刷になったとか。2003年初版なので私自身は当時読んだ可能性が高いが、すっかり忘れていて面白く読んだ。戦前戦後の文系学生の教養主義について彼らの出身階層、読書傾向のデータ、証言をもとに再構成している。戦前と戦後を往来する叙述がやや読みにくいが、著者の実感を交えた分析(2)が面白い。私自身は70年代に学生生活を送ったので、ここに描かれた階層差、地方と都会の差、教養主義が良く分かるとともに、消費文化の勃興期でもあったので、当時を思い出し懐かしかった。 2025/04/14
逆丸カツハ
66
ずいぶん前(8-9年前)から気にはなっていたが米津玄師がべらぼうに面白いと言っていたので手に取る。ホンマやん…。面白かった…。もっと早くに読めばよかったな。本当に自分は芋臭い人間だなぁと理解する。本読んで人格がよくなるかというと、そうでもないだろうとは思うが、教養主義的なものをすべて捨てるのもまた何か違うのだろうなぁ。2025/04/01