内容説明
文久二年十二月、会津藩主松平容保は京都守護職として、風雲急を告げる京に入った。“薪を背負って火に飛び込むような”悲壮な決意のもと、容保と藩士は孝明天皇と都の警護に専心する。だが一橋慶喜らによる改革は実を結ばず、大政奉還、鳥羽伏見の戦いへと転落の道を辿る。幕府と運命を共にせざるを得なかった会津藩の悲劇はここにはじまった。新発見の『幕末会津藩往復文書』が明かす会津藩士の苦渋の日々とは。
目次
第1章 京都守護職
第2章 激動の京都
第3章 薩摩・会津同盟
第4章 長州との確執
第5章 禁門の変
第6章 容保の政治
第7章 孝明天皇崩御
第8章 徳川絶対主義国家
第9章 慶喜逃亡
著者等紹介
星亮一[ホシリョウイチ]
1935年(昭和10年)、仙台市に生まれる。東北大学文学部国史学科卒業。日本大学大学院総合社会情報研究科で日本近・現代史を学ぶ。作家、東北福祉大学講師。東北史学会会員
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
skunk_c
56
京都守護職に就いた松平容保を中心に、幕末の京都情勢とそれに対する会津、さらに徳川慶喜の動きを描いている。特に長州との確執はかなり詳しい印象。容保以外の重要な藩士についても丁寧に紹介され、特に秋月悌次郎、広沢富次郎を重要視している。20年前の書であり、池田屋事件などやや古いかなと思われる記述があったり、龍馬暗殺薩摩説、孝明天皇毒殺説などをかなり可能性が高いとするあたりは、他書との併読が必要だが、読みやすく、人物描写も細かいので、幕末史を深めるのには現在読んでも価値は高い。ちなみに著者は元新聞記者とのこと。2021/04/07
ナツメッグ☆
5
頑迷固陋のイメージが強かった会津藩と松平容保だったが、それなりの危機感、それなりの藩政改革の意志を持っていたことを知った。地政学的に長州、薩摩に比べると不利だったのか。「朝敵」とするには忍びない。徳川慶喜、才はあったのだろうが政治的に縦横さが欠け、会津藩はその犠牲になった気がする。2013/11/02
かに
4
幕末の会津藩・松平容保の思考や動向を解説している。勤王の藩でもあり、幕府に対しても忠誠心の厚い藩であるため、孝明天皇の死後は特に両者の板挟みに合う。会津藩や幕府に対して信頼が厚く、攘夷派の孝明天皇の死は大きな後ろ楯を失う大きなターニングポイントだった。忠誠心の厚く、不器用で駆け引きの苦手な藩のため都合よく使われてしまい、政争に負けてしまい、そのため悲惨な運命を辿るが個人的にはそういった一途な藩は好き。保守的で昔からの慣習や上下関係にこだわりが強い藩なため藩内の人事にも悪影響を及ぼす場面もあった。2023/07/01
UMA
3
新選組史料をある程度読んだところで会津藩(というより容保様)のことも知っておきたくなり購入。会津藩公用局は薩長の動きをきちんと察知した上で狂おしいまでの危機感を持って懸命に状況を打開しようとしていただけに、幕府や慶喜が肝心なところで、それも一度や二度でなく失策を犯すのが腹立たしい。朝廷への畏敬と幕府への忠義に呪縛され続けた会津(というか容保様)と新選組という集団はよく似ている、と思う。2011/11/12
富士の鷹
2
悲壮な決意のもと、京都守護職を引き受けた松平容保。情勢は幕府方にどんどん不利になっていく中、体調を崩しながらも職を全うする容保。辞職、会津帰還を願い出ても将軍慶喜や皇室からの慰留に従い、京を離れること叶わず戊辰戦争で壊滅的な敗北を喫し、慶喜には裏切られ、この期に至ってようやく会津へ戻ったものの(敗走)その時は会津での官軍との悲劇的な戦闘。自虐的と思えるほどの皇室、徳川宗家への忠誠心であるが、ちょうど「逆説の日本史16」で会津藩始祖の保科正之の思想について読んだばかりであったので、この行動も納得。2010/01/31
-

- 電子書籍
- ダッシュエックス文庫DIGITAL 2…
-
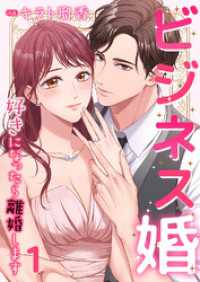
- 電子書籍
- ビジネス婚ー好きになったら離婚しますー…







