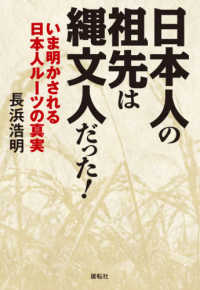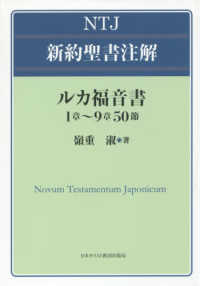内容説明
戦後日本の最大の争点であった防衛問題は、冷戦の終結・五五年体制の崩壊とともに政党間の対立軸としての意味を失った。90年代最大の課題であった「政治改革」は政策不在の状況で追求されたのである。その中にあって唯一の明確な政策パッケージは80年代の中曽根行革の流れを継ぐ「新自由主義」であるが、これに対抗する一貫した議論は未だ存在しえていない。細川護煕、小沢一郎、橋本龍太郎等の政策を分析し現代政治の課題を問う。
目次
第1部 政界再編の中の政策対立軸(55年体制下における政策対立;政界再編の中の対立軸;「第二」の政党―90年代に登場した二つの「民主党」)
第2部 平成不況の中の橋本行革(1990年代中期における日本の経済社会;「橋本行革」の登場、展開、挫折)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ほりほり
2
日本においてネオリベやネオコンは対立軸となり得たのか(なり得るのか)という疑問に答えてくれる書。99年発行だが現在の日本政治を考えるのにも参考になる。ただ防衛・外交問題を対立軸とした55年体制において、政治文化をめぐる社会的亀裂が存在していた、というのは些か単純すぎるのではないか。2014/05/12
のん
1
新自由主義を導入してきた欧米諸国は、失業問題が深刻化し、却って左派勢力が復権を果たしている。一方、日本では新自由主義の負の側面が、未だ顕在化しておらず、したがって、新自由主義の見直しと社民主義の再生には未だ至っていない。1999年に発行された本書ではあるが、この指摘は未だに意味を持つように思った。2017/11/12
ア
1
私が生まれた頃の日本政治がどのようなものであったか掴むことができた。筆者もいうように、現代日本の政治には政策における対立軸がなく、与野党という構図しかないように思われる。打開点はどこに見出し得るのか。 また、新保守主義と新自由主義は1970年代以降結びつき、今でも力を持っているが、この両者の結びつきは自明だろうか。コンフリクトはないだろうか。2016/07/14
きやてい
1
日本政治の対立軸が55年体制期は「防衛問題」を軸としていたが、その後明確な対立軸は無く混沌としている、当時の日本政治をイデオロギーの観点から捉えた本。ということで次は『イデオロギー』を読もうと思います。個人的には、日本企業の社民的慣行に注目し分析した4章は面白かった。2013/08/03
遠山太郎
1
1970反医師会・新保守主義 金融物価政策が評価になったことはない 80教育・宗教・放送批判 82 中曽根 大企業に対する優遇税制はそこで働く労働者サラリーマンにとっても間接的に利益配分となっていると意識されていたのでは 89マドンナ 92鳩菅 93日本新 94村山河野 96民主 橋本 大店舗法には明確に反対していた2011/05/28
-
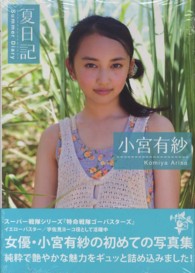
- 和書
- 夏日記 - 小宮有紗