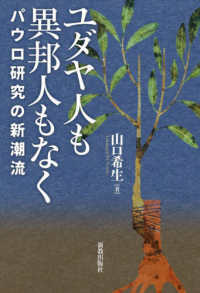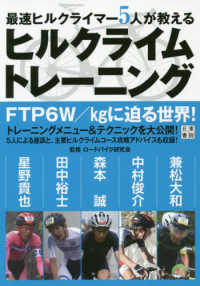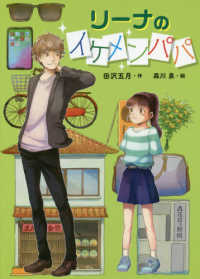内容説明
第一次大戦勃発後、山県有朋を頂点に戴く藩閥官僚政府は、日露の提携によって米英に拮抗しながら大陸での勢力拡大を狙うが、ロシア革命によってその戦略は挫折する。そこで、政治の実権は、対米英協調を唱える原敬に委ねられ、ここに日本初の本格的な政党内閣が誕生した。本書は、日本の政治が、元老指導から議会主導に移行していく時期の潮流を、原と山県の国家構想とそれに基づく対外・対内政治行動から検証するものである。
目次
第1章 第一次世界大戦期の原と山県
第2章 原政友会内閣の成立
第3章 大戦開始以前の原と山県
第4章 外交政策の転換
第5章 原内閣の内政と山県閥
終章 原・山県の死とその後
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Tomoichi
28
原敬と山縣有朋、どちらも好きです。明治政府の創業者の一人である山縣と次世代の原では考え方が違うのは当然で、山縣の親露政策もロシア革命がなければと思ってしまう。原が暗殺されてなければと思うが、歴史とは残酷である。そして原の暗殺後程なくして山縣が亡くなるのも歴史の不思議である。そして混迷の時代へと日本は進んでいく。2025/07/06
スズツキ
6
山県有朋が議院内閣制に否定的だったのは有名。それはテキストレベルだと「旧時代的」「権威主義」と受け取られるけども、しかしその理由は「国際情勢や直近の問題に目を向けず、政党の利を目論み、他党と足の引張あいをするから」だったのか。なんと現代人の耳に痛い話か。2014/11/05
denz
6
近年は新英米派としての評価が定着されつつある山縣有朋の外交構想は、あくまで日本の満蒙権益を維持拡大するためであり、日露戦争後のアメリカのドル外交後はロシアとの協調・同盟によって英米を牽制することで大陸進出を図る。しかし、ロシア革命によってその構想は崩れ、親米路線によって大陸への経済権益を確保しようとする原敬が政権を奪取する。米騒動のような国内の混乱のためではなく、外交構想が原政権を可能にしたというのが、本書の主張。本書構成が原政権前夜、それ以前の原・山縣の略歴、原政権という順番は少々読みにくい。2013/01/09
スプリント
5
平民宰相原敬と維新最後の元老と言われる山県有朋を軸に2つの大戦の間に日本の政局はどのような動きをみせていたのかが語られています。帝政ロシアが存続していたら、、、、米英強調路線を貫いていられたら、、、、歴史に触れる醍醐味の一つである様々な「if」を考えてしまいます。2014/01/18
かに
3
原敬と山県有朋について。主に原敬中心。日露戦争後から第一次世界大戦前・中の山県有朋はロシアとの関係強化、袁世凱政権への支援を中心に中国への日本の影響力拡大をはかり、大隈政権・寺内政権に託した。しかし、強硬な対中政策は反日感情を生み、また、ロシア帝国崩壊により上手く行かず、原敬に政権を託すことに。原敬の外交政策は対英米強調、中国の政権に対しては中立等の政策により、外交は持ち直す。2023/04/09