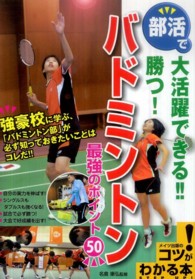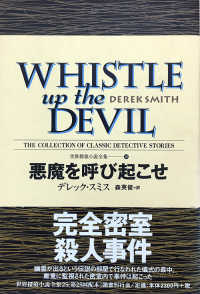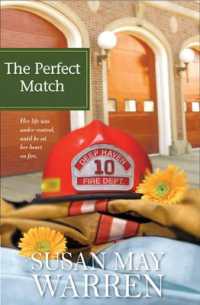内容説明
生命とは、刻々の創造の連続である。複雑な環境の中でリアルタイムに創出される知、即ち生命知がなければ生命を維持することはできない。著者は生命的創出知という新しい観点から「場」の文化を深く捉える方法を発見し、今日まで四百余年の命脈を保つ柳生新陰流の術と理にその知を見出した。本書は生命システムの普遍的な性質を追求しつづける著者による「創作的場所論」の確立と、それによる近代文明超克に向けてのテーゼである。
目次
1 場所とは何か(生命的な知;関係的表現の場;自己言及とシナリオの創出;脱学習と創造;場所的創造;創造における「主語」と「述語」)
2 剣の理と場所の論理(リアルタイムの創出知―柳生延春氏への手紙;剣の理と場所の論理―柳生延春氏との対談;即興劇モデルの追求―柳生延春氏への手紙 第二信)
3 柳生新陰流の術と理(流史;術と理)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
無重力蜜柑
12
異様な書だ。創造性、開放性、自己認識、フィードバックループ、ストーリーの生成……。古い本なのもあり、ネオサイバネティックな主題自体に目新しさは特にない。しかし、この本は生命論を柳生新陰流の剣理に結びつけてしまう。先に敵に斬らせてから斬る新陰流の極意「まろばし」。それを可能ならしめる彼我の「拍子」の同調は筆者曰く生命知と等しいらしい。脳科学や生理学を論じながら西田幾多郎から引用した独特の用語で思弁を展開し、日本の伝統文化たる剣術を家伝書から分析する。まさに二十世紀という感じの胡乱さで、嫌いではない。2024/06/04
Hiroki Nishizumi
3
薄い新書でありながら、濃い内容と学者らしい緻密な定義、さらに重層的な論理展開が多く、文章そのものは平易ながら要点の取りまとめは苦労した。読むことそのものは誰でも抵抗なく読み進められると思う。武道を行わない立場で武道を説明するところが新鮮で役に立った。2013/04/26
r_ngsw
1
この本自体は1996年に書かれたもので、今のAIの状況とかは知るべくもない時代でしたが、中では既に来るべき人工知能時代を予想されていたような記述もあります。そこでも人間はコンピューターに取って代わられるのかどうか、ということについて、即興劇と柳生新陰流を題材に、 続きはこちら→ https://goo.gl/krsKZh2017/12/20
הזם
0
「上」の人たちが「上」のことについて議論している風景を、時折やさしく提示される例を借りつつ、何とかkeep up withする楽しい読書体験。創造とは何かという問いに、ここまで漸近できるのかと驚いた。読み返しつつ、参考文献をあさりつつ、生命と創造についてゆっくりと自分なりに考えていけるといいな。2015/05/19
Hiroki Nishizumi
0
導入からぐいぐい惹きつける。 戦国の刀法が最高の結実に達したとき、その結実を代表する宮本武蔵と柳生兵庫助の二人が尾張徳川家の名古屋の城下に約三年間も同時に暮らしていた─── 錬士の頃に読むとちょうど良い気がする。いずれにせよ良書だ。 2012/01/21
-
- 洋書
- Jane Eyre