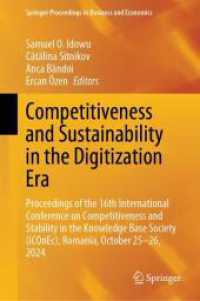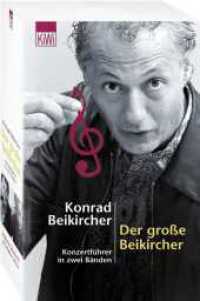- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 哲学・思想
- > 構造主義・ポスト構造主義
内容説明
1930年代のブラジル滞在中に撮影した写真180点に文章を添え、『悲しき熱帯』から39年後の1994年に刊行された写真集。先住民との出会い、ファインダー越しにとらえた彼らの表情―。20世紀最高の知性の1人とされる人類学者の若き日々の体験を鮮烈に伝える、稀有の記録。
目次
ブラジルとの出会い(サン・パウロとピラポラ;イタティアイア山;パラナ、サンタ・カタリーナ;ゴイアス)
カデュヴェオ族からボロロ族へ(カデュヴェオ族;ボロロ族)
ナンビクワラ族の世界
アマゾニアで(ムンデ族;トゥピ=カワイプ族)
帰途
著者等紹介
レヴィ=ストロース[レヴィストロース][Levi‐Strauss,Claude]
1908‐2009。1908年11月28日、両親の滞在先のベルギーで生まれる。パリ大学卒業後、リセで哲学教師を務めたのち、35年、サンパウロ大学社会学教授としてブラジルに赴任、インディオ社会の実地調査にあたった。59年、コレージュ・ド・フランス社会人類学講座の初代教授となり、73年にはアカデミー・フランセーズ会員に選出された。82年、コレージュ・ド・フランスを定年退職。著作は人類学のみならず、人文科学、思想、文化全般に広汎な影響を与えた。2009年10月30日午後、パリの自宅で逝去
川田順造[カワダジュンゾウ]
1934年(昭和9年)、東京に生まれる。東京大学教養学部教養学科(文化人類学分科)卒、同大学大学院社会学研究科博士課程修了。パリ第5大学民族学博士。東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所教授、広島市立大学国際学部教授、神奈川大学大学院歴史民俗資料学研究科教授を経て、神奈川大学特別招聘教授、神奈川大学日本常民文化研究所客員研究員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
かんやん
朝日堂
まふ
読書家さん#2EIzez