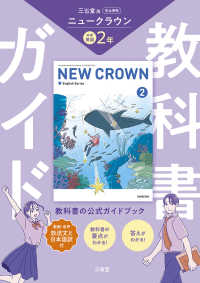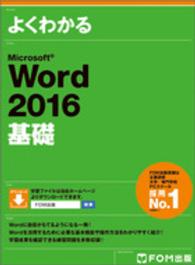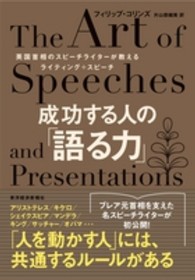内容説明
伝統的な「英米との協調論」から、対英米開戦に最後まで反対していたといわれる海軍。しかしながら、戦前の日本海軍は、戦間期に英米との協調を象徴していた海軍軍縮体制を最終的に拒絶し、また、日中戦争遂行の中で将来の対英米戦に向けた態勢作りに腐心していた組織であった。従来、こうした動きは一部強硬派の突出とされてきたが、本書ではあらためて、海軍全体を通した「英米との対峙論」から、その「真珠湾への道」を探る。
目次
第1章 「海軍休日」との決別
第2章 ドイツへの傾斜
第3章 蒋介石との対決
第4章 南進への布石
第5章 太平洋上の満洲事変
第6章 三国同盟の戦略
終章 対英米開戦への道
著者等紹介
相沢淳[アイザワキヨシ]
1959(昭和34)年宮城県生まれ。防衛大学校卒業。上智大学大学院博士課程修了。91年から防衛庁防衛研究所に勤務。95年から96年にかけて、ロンドン大学(LSE)客員研究員。現在、防衛研究所戦史部主任研究官
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。