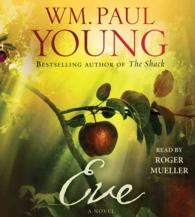出版社内容情報
日本人は欧米からいかに学んで近代国家を築いていったのか。幕末から明治期の文豪や欧米派遣団員らの興味深い日記を丹念に読み込む。
アメリカへ、欧州へ。幕末・明治期に海を渡った日本人の「見聞録」が面白い!近代国家へと歩み始めた幕末から明治時代、日本人は何を考え、何を見ていたのか? 今に残る膨大な数の日記から三十余篇を選び出し、「世界」は彼らの目にどう映ったのか、そこから何を学んでいったのかをつぶさに眺める。鴎外、漱石、荷風らの作家、政府派遣団員に密航者、そして何人もの女性と、興味尽きない人々が登場。
内容説明
近代国家へと歩み始めたこの時代に、日本人は何を考え、何を見ていたのか。鴎外、漱石、荷風ら作家に、政府派遣団員、密航者、女性、そして国内で活躍した人々の興味尽きない日記30余篇を読みこむ。徳川幕府や明治政府の派遣団員の日記は詳細を極め、蝦夷や沖縄の探訪記は現地の状況をまざまざと伝える。見事な好対照を成す鴎外と漱石の留学記に、それ自体が最高の文学となった啄木のローマ字日記…。キーン氏の眼力が日本人の文章に込められた本質を発掘していく。
目次
序 近代日本人の日記
1 初期米欧派遣団員の記録
2 中国へ、北へ、南へ
3 のちの文豪たちと密航者
4 政治家も日記を付けた
5 女性の見た日本と世界
6 明治日記文学の傑作
7 二十世紀に入って
終わりに 近代の旅人たちの西欧との出会い
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ふくとみん
2
木村摂津守・司馬遼太郎は否定的に書いていたが「相手に感銘を与えながら振る舞うことのできた日本人」であることがわかった。 松浦武四郎・今まで夢物語として書かれたものしか読んでいなかったがアイヌ民族の姿がわかり感動した。 徳冨蘆花・現代では許されることはないような話に驚いた。 若いときのエネルギーをつぎ込んだドナルドキーンの作品に感謝するしかない。2023/12/24
ブルーツ・リー
2
「日記文学」というフィールドを開拓した人、と言えるのかな、ドナルドキーン先生は。 日記も、大作家の全集ともなれば載っている事も多いのだけれど、ドナルドキーン先生の場合、殆ど名も知られて居ないような一般人の日記まで読み漁り、感動した作品については批評を加えて、それらを文学の高みにまで登らせました。 ある意味で人の本心が、小説以上に書かれるのが日記で、特に石川啄木あたりに関しては、小説家としては失敗に終わったものの、ドナルドキーン先生の手にかかれば、日記作家としての復活を果たせそう。日本文学に新たな地平が。2019/12/12
なんとかさん
1
最後の方は大分駆け足で読んだのだが、幕末あたりに書かれた日記を解説したところは非常に興味深く読めた。「続」の方を先に読んでしまったので、その前の本も読もうと思う。2015/09/11
Hirokazu Ikuta
0
幕末期から明治までの日本人の日記を読み比べ。当然ながら、後世に残っている日記は、幕末に海外を旅した記録を残したものが多い。キーン氏は、日本人が西欧文明に初めて触れたことの印象を読み比べているが、そもそも日記を残しているのは武士階級の人なので、武士のプライドが邪魔して書かれていない本当の印象はどうだったのかに想いを巡らせる。キーン氏がある日記の著者に親近感を感じて、できることなら会って話したかったと語る、日記への感情移入は、本当に日記が好きなんだなと、感心しきり。2016/04/15
大猫熊
0
いつ読み終えるかわからない。虚構の創作と事実の創作とで文学評論を画すると日記を文学とするのはかなり困難だ。ひとつひとつを読むたび、読まなければよかったという思いが過ぎる。キーンさんを読み続けることの困難は、やはり全集でも同じかと感じる。翻訳を通して現代語訳で捉えてフィルターをかけての作品の享受は死を賭した兵士の手記とは異なるだろうに、解読の手法が同じなのか、自ら研究ではないと言っているのだから、首肯するしかない。自伝文学がジャンルとして成立しなかったから、その代替のように読むといいのだろう。読み続けよう。2012/05/04