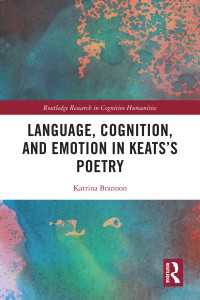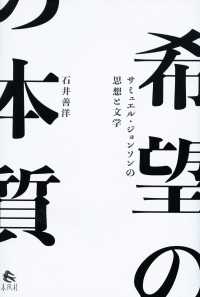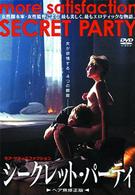出版社内容情報
「メジャーを目指しているので、頑張るのはそこじゃない」。高校野球の現場で進む変化を追う。
内容説明
二〇一九年夏、岩手県大会の決勝で大船渡高校のエース、佐々木朗希が登板を回避したことは、賛否の論議を呼んだ。それは突き詰めると、「甲子園にすべてを捧げる」か「将来の可能性を取る」かの選択に他ならない。「負けたら終わり」のトーナメント方式の中で、どう選手を守り、成長させていくのか。球数制限、丸坊主の廃止、科学的なトレーニングの導入など、新たな取り組みを始めた当事者たちの姿を追う。
目次
第1章 新潟県高野連はなぜ、球数制限導入を決断したのか
第2章 「甲子園」に取り憑かれた鬼軍曹の改心
第3章 「プロでは大成しない」甲子園強豪校の代替わり
第4章 メジャー帰りのトレーナーと進学校がタッグを組んだ理由
第5章 激戦区の公立校からはじまった「球数制限」と「リーグ戦」
第6章 丸坊主を廃止した二つの私立強豪校
第7章 サッカー界「育成のカリスマ」の試みから見えるもの
第8章 テクノロジーが、選手を強くする
著者等紹介
氏原英明[ウジハラヒデアキ]
1977(昭和52)年ブラジル・サンパウロ生まれ。スポーツジャーナリスト。奈良新聞勤務を経て2003年に独立。03年の夏以降、甲子園大会はすべて現場で取材している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
金吾
23
勝利至上主義と決別というより、視点を拡げたもしくは一元的なもののとらえ方ではないという話に思えました。金沢監督や中谷監督の話が面白かったです。2025/01/22
マッちゃま
20
令和の高校野球について書かれた本。甲子園…春も夏も楽しみで、素人スカウト目線で噂の好投手をチェックし「こりゃ凄い!」と思った投手は直ぐに負けてほしいと切に思ってます。なぜなら、勝ち進むと肩や肘を故障するリスクが高すぎるから。昔から言われていた事なのに勝利至上主義の名の下に放置されていた大問題。その大問題の解決に動き出した県や人物、高校を取材したのが本書。選手ファーストと叫んでも選手によって考え方も千差万別ではないのか?ただ、長い人生で甲子園とは通過点であると言ってくれる人物が居れる場所は必要だと思います。2022/02/14
ta_chanko
18
球数制限で選手の肩肘を守るとともに、多くの選手に出番を与える。選手を調教し服従させるのではなく、対話を重ねて主体的に考えさせる。根性論ではなく、テクノロジーやデータを活用して成果を可視化する。負けたら終わりのトーナメントではなく、リーグ戦を導入して出番を増やすとともに、失敗できる状況の中でチャレンジさせる。丸坊主をやめる。今は時代の過渡期。いつまでも古い慣習に囚われていると、野球が滅びる。いや野球だけでなく、社会のあらゆる分野にも共通して言えること。2021/09/20
もちもちかめ
16
野球専門のフリージャーナリストはどうも読みにくい。著者の文章の素養がなってないのか、行間が上手く読めない。いや、私の野球界の行間を読む知識の決定的不足。それくらい、野球界は難しい。闇というか、まじで単にコネ。このインタビューをとる価値が、この人選の価値が上手く解らない、計れない。言葉の裏が読めない。もやもやしますね本当。智弁和歌山の監督の話を聞いて智弁学園の監督でない理由。そういえば、イチロー、智弁和歌山に初めに指導に来たよね。別に大阪桐蔭や星稜で良いのにさ。ね、闇でしょう。いや単にコネだけど。2022/02/09
夜明けのランナー
12
整列、行進、連帯責任、勝利至上主義、高校野球における連想ゲームは美化されている。それは教育であってスポーツや職業選択とは異なるからかもしれない。野球人口が減少するなかで、いかに優秀な人材を育成するか。しかし、それは誰のために?とも思えてしまう。 僕は高校野球が大好きなので、いろいろな人の意見を参考にしつつ、メンバーやスタンドて応援している全てのひとに感謝したい。2021/09/11